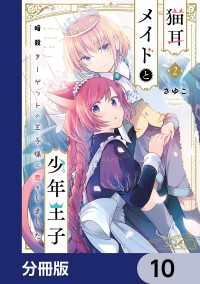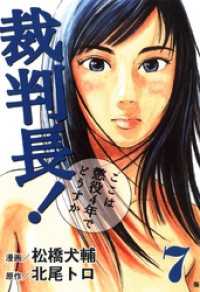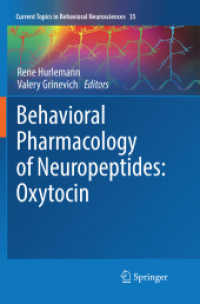内容説明
子どもたちに「汎用的能力」を育てるために、「教師力」「授業力」を磨こう!21世紀型学力を育むには「探究」「協同」が鍵!アクティブ・ラーニングで子どもと教師は変わる!思考ツールの活用法がこの1冊で分かる!
目次
1 21世紀型学力を育成する授業(21世紀の社会に求められる人材;21世紀の社会に求められる汎用的能力;汎用的能力を育成する要の時間としての総合的な学習の時間 ほか)
2 教師力を磨く―イメージ力のすすめ(求められる教師の意識変革;教師力はイメージする力;イメージ力豊かな教師が行う単元づくりと授業づくりのポイント ほか)
3 授業を磨く―アクティブ・ラーニングのすすめ(授業の質的転換;授業の質的転換に向けたアクティブ・ラーニング;自発的・能動的に学び始める課題設定の場面 ほか)
著者等紹介
田村学[タムラマナブ]
文部科学省初等中等教育局。教育課程課教科調査官。国立教育政策研究所教育課程研究センター。研究開発部教育課程調査官。昭和37年新潟県生まれ。新潟大学教育学部卒業後、昭和61年4月より新潟県上越市立大手町小学校教諭、上越教育教育大学附属小学校教諭、新潟県柏崎市教育委員会指導主事を経て、平成17年4月より現職。日本生活科・総合的学習教育学会理事も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
motoryou
6
分かりやすいし、伝えやすい。職場で活用することもできそう。2015/06/21
Riopapa
5
一度、講演を聞いたことがあり、購入。ここ1年でアクティブラーニングのことは大分分かってきたつもり。どのように授業実践に移すか。アクティブラーニング導入の背景が分かったのが良かった。2016/02/27
totuboy
4
次の学習指導要領の改訂に向けてもう動き出している中、この本はそれを先取りするような内容が盛り込まれている。おそらく、ここに書かれていることが次の指導要領ではメインとなってくるであろう。これからはどの教科でも「構成主義的」な授業が大切となってくる。時代に応じた力を育てていくために、ぜひ現場の教員が読むべき本である。思考ツールについてはムックでそれだけに特化した本があるので、それを読んでもよい。2015/05/25
epitaph3
4
2015年231冊目。文科省調査官が語るだけあり、それだけで、何か、「この国の教育は、授業の質の転換を図らんといかん」という気持ちが襲う。実際にそう思う。一斉指導だけではなく、学習者が主体の取り組みを!という流れは、進んでいる。そして、その取り組みによって、子どもがどう変わるか、授業の後にどう変わっているのかを、「イメージ」できるか。また逆に、「イメージ」して、そのような子どもにするためには、どのような内容を組んでいけばいいのか。これって、生活単元学習にも似ている気がする…。後半の学習ツールもおもしろい。2015/05/05
KTakahashi
3
アクティブ・ラーニングについて勉強しようと思い購入した本の中の1冊。そもそもの出発点の資料のありかが判ったのが第1の収穫。 読んで見て,自分一人で考えるときに,思考ツールをつかった思考法があったが,それを複数人数で行うことにしたらどうなるか。逆の考えもできる。複数人数で行うブレインストーミングを一人でやったらどうか。 この本によると, ①課題を見つけ,②情報を収集して,③整理・分類して,④気づいたことや考えたことをまとめて発表したり,行動したりする。 初期の「総合的な学習の時間」にやっていた取り組み2016/01/14