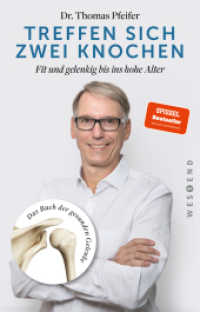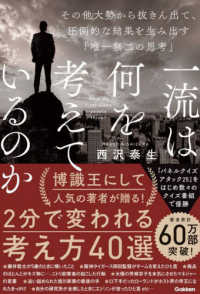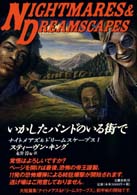内容説明
教師生活30年超、筑波大学附属小のプロ教師が「クラスをまとめる秘訣」を大公開!
目次
第1章 子どもが変わる最初の一歩―仕掛けて、待つ(「子どもが自分で考える場」をつくる教師の仕掛け;最初は、あえてあいまいな指示を出す ほか)
第2章 「点」ではなく「面」で見る―子どもを見る(実践!「子どもウォッチング」のすすめ;子どもを「点」ではなく「面」で見る ほか)
第3章 ほめるための仕組みをつくる―ほめる・叱る(子どもが変身するほめ方とは;クラスが動く「ほめ方の三段ロケット」 ほか)
第4章 一人の子どもに変化を起こす―変化を広げる(「一人の変化」が「クラスの変化」を起こす;学級づくりと授業づくりは同時進行で ほか)
第5章 保護者と一緒に変化を起こす―周りを巻き込む(保護者を巻き込むのも一つの方法;小学校は人間関係を学ぶ最高の環境 ほか)
著者等紹介
田中博史[タナカヒロシ]
1958年山口県生まれ。1982年山口大学教育学部卒業、同年より山口県内公立小学校3校の教諭を経て1991年より筑波大学附属小学校教諭。専門は算数教育、授業研究、学級経営、教師教育。人間発達科学では学術修士。共愛学園前橋国際大学非常勤講師・基幹学力研究会代表・全国算数授業研究会理事・日本数学教育学会出版部幹事・学校図書教科書「小学校算数」監修委員。またNHK学校放送番組企画委員として算数番組「かんじるさんすう1・2・3」「わかる算数6年生」NHK総合テレビ「課外授業ようこそ先輩」などの企画及び出演。JICA短期専門委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
江口 浩平@教育委員会
しげ
あべし
y
2h35min