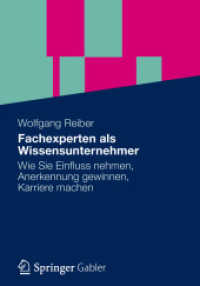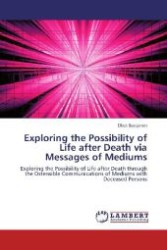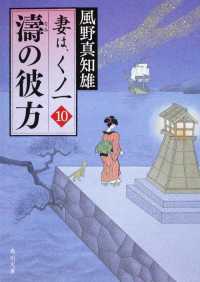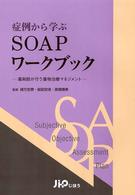目次
概説編(森林政策から見た“徳川三百年”)
基礎知識編(日本の森林;森林の保全と育成;伐木と運材;流通と市場;領主による御用材生産;領民による材木生産;村の生活と森林)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なおこっか
5
ジャレド・ダイアモンド『文明崩壊』に森林保護の成功例として取り上げられた、徳川時代の森林政策の詳細が知りたかったので。秀吉、家康がばんばん城を建てた時点で、このままじゃ森がヤバいと気付いた人々、ほんと尊敬する。数十年単位で育て、数年単位で運搬していた木々を、今や湯水の如く他国から仕入れて消費する日本…。この本の冒頭概説だけでも参考になるが、政権側の方針から、現場作業、最終的な木の使用方法まで、諸々追った後半もなかなか面白かった。伊勢神宮との関係がもう少し詳しく知りたいところ。2019/05/30
Hiroki Nishizumi
3
江戸時代に森林管理がしっかりと行われていたことは知らなかった。時代を越えて官僚たちは優秀だったということだろうか。2022/12/05
Junpei Ishii
2
日本の森林管理の歴史は思いの外浅く、17世紀後半から森林資源が枯渇したため、輪伐制度や植林が行われるようになったという。昭和30年代以降の拡大造林によって、江戸時代に確立した森林管理のノウハウが失われ、日本の森林管理はこれから再構築していかなければならない時期を迎えているのだという。そういう意味では、17世紀後半に当時の森林関係者が直面した状況と現在はよく似ている。近世の森林管理の手法を学ぶ現代的意義を考えさせられた一冊。2012/06/10
相馬
1
朝井まかて「御松茸騒動」→徳川林政史研究所紀要「尾張藩御林の管理・利用形態と松茸」という流れで,読んだ。豊臣→徳川初期の巨大建築ブーム,江戸の火災頻発による森林資源の枯渇,植林,留山(伐採禁止),輪伐の歴史や切り出し,輸送,材木問屋など広く,読みやすくまとめてある。序で現在(昭和後期)の営林署の売り上げ至上命令による森林荒廃が述べられているのも意味深。2016/03/15
根室
0
昔は火を起こすにも家を作るにも、木が絶対に必要だった。その木がどうやって作られていたかは意外と知られていないこと。2012/12/05