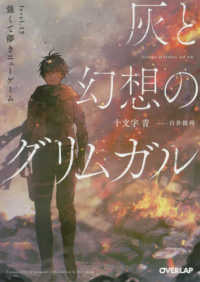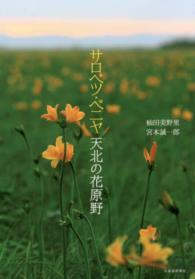出版社内容情報
江戸時代は遊びの天国!子どもたちを描いた浮世絵を800点掲載!新しい視点で「江戸時代の文化・風俗」を紹介した“初の事典”!
新春の凧揚げ、春には桜の木の下で相撲、初夏の蛍取りから冬の雪遊びといった四季折々の遊びから、芝居ごっこ、火消しごっこなど大人の真似遊び、そしていつの時代も変わらない、いたずら、けんか、落書きに至るまで、当時の子どもたちの遊びをヴィジュアルで紹介、解説を付けました。掲載する浮世絵は802点を超え、そのほとんどが学習塾・日本公文教育研究会(くもん)の「くもん子ども浮世絵ミュージアム」が収集、所蔵しており、同研究会が全面力の下、江戸時代の子ども文化をまとめた“初めての事典”となります。
【本書の特長】
?江戸時代に見られた子どもたちの遊びを50音順に並べ、図版とともに遊びの内容、解説。
?紹介、解説をつけた遊びは、200項目を超える。
?掲載の浮世絵は、鑑賞に値する美しさをも提供。
?遊びの名称は、江戸時代および明治初期の文献と絵画史料から、代表的な呼称を選び立項。
?巻末には、本文中で紹介した絵師、絵師別作品一覧、総索引を付ける。
監修のことば
はじめに
凡例
本文(50音順)
コラム
総索引
参考文献
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Fumie Ono
1
江戸時代の子どもの遊びは戸外が主役。この時代、子どもは家や地域の宝とする「子宝思想」が普及していたとあり、おおらかに遊んでいたようだ。冬は雪遊びが盛んで「火消しごっこ」「雪転がし」「氷たたき」「雪中竹馬」等々遊びの工夫が興味深い(電気がないから当然か)。とりあげられた遊びは200項目、掲載された浮世絵は800点余り。解説も面白いが、浮世絵から当時を思い巡らすのも楽しい。北斎、広重や歌麿の子ども絵では、いままで知らなかった絵師の一面をみることができる。江戸時代の文化・風俗を知る上でも貴重な一冊だと思う。2014/12/23