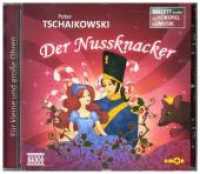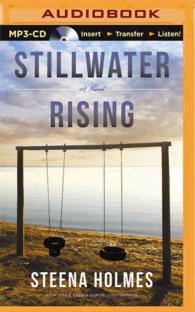出版社内容情報
古代中世の名乗りは本貫の地や職業・地位、出生を示す史料である。古来の姓氏から現代の多数姓・名前まで、その変遷を解説する。
内容説明
古代・中世の名乗りは、そのまま個人の職業や地位、出生や血脈を示す奥の深い史料でもある。古来の姓氏から現代の多数姓・名前まで、その変遷をひもとき、興味つきない歴史世界へといざなう。
目次
第1章 名前の見方・とらえ方(日本人の名前のはじまり;名字と苗字)
第2章 苗字と名前の歴史(氏名と姓名―古代の社会と名乗り;名字と苗字―武士の社会と名乗り;諱と通称―実名の変遷史)
第3章 現代の名前(苗字と名前の近代化;名前から歴史を読む)
著者等紹介
奥富敬之[オクトミタカユキ]
昭和11年東京都生まれ。昭和46年早稲田大学大学院文学研究科史学専攻国史専修博士課程修了。日本医科大学歴史学教室専任講師。昭和61年同大学同教室教授。平成14年同大学定年退職、名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
獺祭魚の食客@鯨鯢
49
日本人の苗字の多さには理由がある。氏姓制度から始まった日本の血統が姓は母系社会により、氏は父系社会に変遷したことに起因するからのようです。 姓の文字は女偏に生きるですからなるほどと思ってしまいます。同じ母親から生まれた子が同族として扱われる。父親が貴種であればその一族の社会的地位が上がる。藤原氏は千年以上にも渡り日本の中枢に留まり続けたのは外戚を独占できたからです。 源平藤橘の分家として居住地にちなんで氏を創設したことが苗字の増加となった。例えば加賀の藤原は加藤というように。 2020/10/03
のら
3
氏、姓、称号、名字、苗字を詳しく説明。由来、歴史など大体わかる。諱、通称の歴史も十分だ。良かったのは源九郎義経の九郎にあたるのが「輩行の仮名」という呼び方であると分かったこと。茶屋四郎次郎なら四男である父親から生まれた次男となる。佐々木小次郎なら次男である父親から生まれた次男=次郎次郎、略して小次郎。那須与一なら、与は余の代替で十にあまる意味。つまり与一は十一男。庶民でも古代から氏名(うじな)を持っていたとか、領地由来の複合姓とか、妻が夫の姓になるのは明治期に西洋を真似したとか非常に興味深い。2016/05/04
narmo
1
必要があって読み始めたけど、意外と面白かった。万葉集に出てくる、読みにくいややこしい名前の謎が解けて、特に謎を解きたいと思ってなかったのに、妙に嬉しいです(^o^) あと、貶姓で「清麻呂」を「穢麻呂」にしたとか、すごすぎるんですけどー!2018/07/16