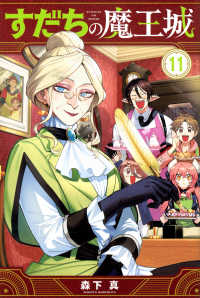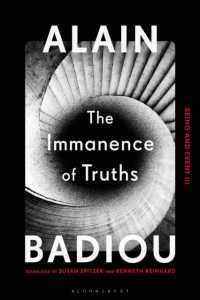内容説明
落ちめの弱小電子オルガン業者が、起死回生の策として打ち出した新商品。それは精巧な模造人間の製造だった。宇宙開発用ロボットを改造し、歴史上の人物に関する生前のありとあらゆるデータを詰め込んで、この世に“再生”させたのだ。だが誰もが驚いたことに、そいつらは人間以上に人間らしかった。彼らはこれをアメリカ一の実業家に売り込もうと画策するが。ディック中期の名篇。
著者等紹介
佐藤龍雄[サトウタツオ]
1954年生まれ。幻想文学翻訳家
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
催涙雨
54
嫌いな作品ではないが、小説としての完成度ははっきり言って滅茶苦茶。その手の象徴としてあげられるザップガンよりも個人的にはひどいものだと思う。前半と後半に繋がりを見出すのが難しく、やたらに投入されるガジェットのすべて、特に一番大切なはずのシミュラクラですら作品の結末に寄与しない。最たる例であるリンカーンのシミュラクラは、過去を掘り下げつつ主人公ルイスとの共通点を見出したり、重要な位置を占めるキャラクターであることを再三匂わせた挙げ句にルイスに二言三言助言する程度の活躍で脇筋に追いやられ、登場すらしなくなる。2019/12/30
藤月はな(灯れ松明の火)
50
「天下のディックだからといって何でもかんでも傑作や名作とつけるのは止めようぜ」と言いたくなった本。人間は利害関係や環境などの外的要因によって移り変わっていき、内面に常に矛盾を抱えているもの。機械は外的要因が何であれ、常に確固たる「己」を保つもの。だからこそ、機械はより理想の人間らしく、人間はより人間らしくない。多分、それを伝えたかったのでしょうが、話がしっちゃかめっちゃかで集中できなかったです。そして歴史上の人物をプログラミングしたシミュラクラのリンカーンやスタントンは一体、何だったんだ・・・。2014/10/31
鐵太郎
12
メカニカルを書きたいのなら、電子オルガンの会社が人間に匹敵する人間型マシンを作れる不条理を、もう少しうまく説明してくれ。主人公が、狂気のままに風呂場にこもってタイルを貼る娘になぜ恋したのか、明確なきっかけを書いてくれ。ディックが、SFから純文学に移ろうとする過渡期なのだそうな。うーん、いまいちか。 2005/10/20
ボブ
7
救われない結末、主人公の絶望諦め、評判は良くない作品だが個人的には大好き。2022/04/03
roughfractus02
6
主人公の勤める会社の主力製品が売れず、シミュラクラ(人造人間)を作ることになる。南北戦争時の有名な人物を作るのは、大量に残された当時のデータを打ち込めば精神が生まれるとされるからだ。が、シミュラクラが社会に出始めると物語は主人公の神経症の女性プリスへの愛に変わり、プリスは統合失調と診断されて入院させられ、主人公も同様の過程をたどる。本書の物語の変更については議論があるが、シミュラクラの精神を作る過程で、自分の精神も作られているのではないか?という作者の一貫した問いが現れ、主人公の病と重なる過程が生々しい。2020/05/27