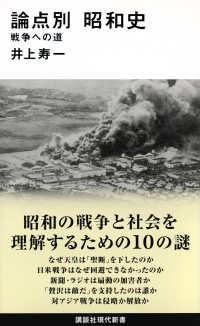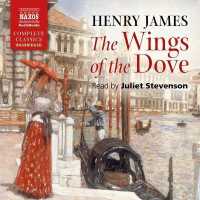内容説明
1841年、エドガー・アラン・ポオの「モルグ街の殺人」により幕を上げた近代ミステリーの歴史は、1964年、わが国の一冊の書物によって本質的にその終焉を告げた。スタイルを探偵小説に借りて時代に捧げられた一冊の供物。絶対主義から全体主義、二つの世界大戦、アウシュヴィッツ、広島・長崎を経験した激動の二十世紀は、ステファヌ・マラルメの「世界は一冊の書物に到達するために存在する」という悲願を、本書によって実現したのであろうか…。中井英夫ならぬ塔晶夫畢生の大作『虚無への供物』が、建石修志の衣装を纏い三十六年ぶりに復活する。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田氏
16
あるギャグ漫画家はこう言った。「人が転ぶのを見るのは可笑しいけど、転んでいる本人は可笑しくない」喜劇であれ悲劇であれ、それをそうあらしめるのは誰の目によってか?事件は事件である資格を得るために犯人を必要とする。要求に応えるべくしてか、迷とつけてもいい推理を繰り広げる素人探偵たち。合理性を見出そうとするがゆえに現出する不合理。どぐ☆マグの並びからすると意外だったが、物語としては一応の合理的解決がもたらされる。奇たる要素ももはや別の言葉で片付けられるのか知らん。だが提示される批判はなお我々を指差し続けている。2020/06/06
カシヤ
4
密室殺人という括りに翻弄されていったのは登場人物だけでなく、読者である自分もだったなと感じました。事件の犯人は明確になっているのに、「それで、犯人は誰だったのだろうか」というなんとも不思議な読後感。久生の自信過剰な感じが苦手でしたが、終盤での牟礼田を逃さまいとするシーンのおかげで一番好きなキャラになってしまいました。読み疲れましたが、手にとって良かったなと思いました。2013/03/04
uchiyama
3
犯罪を生み出しているのは、現実の無秩序を耐え難いとする私たちの意識と、物見高さなのかもしれない、ということを、ミステリそれ自体への批評として剔抉するのがテーマ、だけどそれを娯楽作品に仕立て上げるのって趣味が悪いよね、と作中人物に言わせて逃げも打っておくメタ構造。そんなコンセプチュアルな小説の問題は、やや鼻につく感じはさておき、この長さを読ませるだけの面白さはあるのかってことで。結局は、構造が先立って、へー、よく考えたなぁ、くらいにしか思えないのがなぁ…。圧倒的に面白い山田風太郎の偉大さを思ってしまったり。2025/12/11
ちぇん、
3
奇書という括りから読み辛さを覚悟の上で読んだところ、存外の読み易さに驚く。筆致は意外にも柔らかで軽妙な会話文が多めに配置された文章は現代においてもリーダビリティの高さを発揮している。この文体に加えて、史実の事件や書籍、ミステリ衒学、シャンソン等の時事ネタが作中で登場する。江戸川乱歩曰く「冗談小説」という位置付けなのも頷ける。正統派推理としても読み応えのある内容である一方で、終章にて主張される真相はアンチ・ミステリである。戦後15年という時点で既にアンチ・ミステリとしての到達点に既に至っており、これぞ奇書。2020/02/12
猫ほっけ
2
すごい遠回りだし登場人物達の推理合戦は的外れだけど、そこが楽しかったです。好奇心はほどほどに。2018/09/07
-

- 電子書籍
- ボクは日本一かっこいいトイレ清掃員 岩…