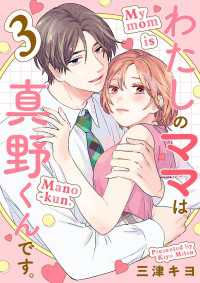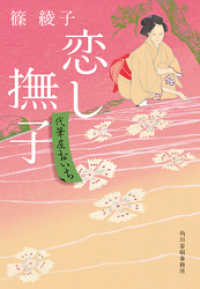内容説明
京極夏彦や森博嗣以降の探偵小説は、キャラクター小説的な色合いを強く帯びてきている。「人物、性格」という意味のほかに、「文字、記号」という意味も持つ「キャラクター」という単語。このキーワードを頼りに、探偵小説に何が起こっているのか、そして探偵小説はどこへ向かおうとしているのかを真っ向から論じる。巽昌章、鷹城宏との往復書簡や、若手ミステリ作家の北山猛邦、辻村深月、米澤穂信との座談会も併せて収録。『探偵小説と二〇世紀精神』に続く画期的な評論集。
目次
1 記号的キャラクターと精神的外傷(ジャンルXという提案;登場人物とキャラ ほか)
2 大量死の経験と「キャラ」(多重人格とキャラ的なもの;内面領域の細分化と表層化 ほか)
3 清涼院流水という「問題」(探偵小説と「あえて」の意識;ポストモダン第一世代と第二世代 ほか)
本格ミステリ往復書簡
座談会 現代本格の行方
著者等紹介
笠井潔[カサイキヨシ]
1948年東京生まれ。79年にデビュー作『バイバイ、エンジェル』で第6回角川小説賞を受賞。以降『サマー・アポカリプス』『薔薇の女』他、矢吹駆を主人公としたシリーズなど数多くの小説を発表する傍ら、精力的な評論活動を展開。98年『本格ミステリの現在』編纂で第51回日本推理作家協会賞受賞。2003年の第3回本格ミステリ大賞では『オイディプス症候群』で小説部門を、『探偵小説評論序説』で評論・研究部門をダブル受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ポン・ザ・フラグメント
aritan
ぐうぐう
ハイザワ
まっち