出版社内容情報
絶海の孤島、南硫黄島。本州から南に1200kmの場所にあり、その開闢以来人類が2度しか上陸したことのない、原生の生態系が残る奇跡の島である。
本書は、その島に特別なミッションを受けて挑む研究者たち(主に鳥類学者)の姿を、臨場感あふれる筆致で描く冒険小説であるとともに、進化や生態についての研究成果報告書でもある。
襲い来るサメ!
崩れ落ちるガケ!
降り注ぐトリ!
噛みつくコウモリ!
大気がハエ!(サメ以外は本当です)。
抱腹絶倒空前絶後の科学エッセイがここに誕生。
内容説明
鳥類学者(川上和人) VS 南硫黄島(本州から約1200kmの無人島)。闇から襲いくる海鳥!見知らぬ、斜面。血に飢えたウツボ!史上最強の冒険が、今はじまる。
目次
第1部 探険・はじめまして編(上陸と幕営と始まりの始まり;学術戦隊ミナミイウォー;アカパラ発見せり ほか)
第2部 熟考・ここが天王山編(島にないものと、島にしかないもの;北硫黄島・パラレル・アイランド;海鳥ヒッチハイクガイド ほか)
第3部 灼熱・宴もタケナワ編(再会・南硫黄島;ここはいつか来た海岸;再び、コルへ ほか)
著者等紹介
川上和人[カワカミカズト]
1973年生まれ。東京大学農学部林学科卒、同大学院農学生命科学研究科中退。農学博士。森林総合研究所鳥獣生態研究室長。南硫黄島や西之島など小笠原の無人島を舞台に鳥を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
83
著者は、森林総合研究所鳥獣生態研究室長で農学博士の川上和人先生。先生の本は「鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ」「鳥類学者、無謀にも恐竜を語る」など4冊を読了。これまで人類が2度しか登頂したことのない、原生の生態系が残る奇跡の島「南硫黄島」における特別なミッションに挑む研究者たちの姿を、臨場感あふれる筆致で描く一冊。相変わらず、小気味良い語り口調でテンポよく展開していて、本来は難しい内容ながらサラッと読めました。2024/08/27
サンダーバード@読メ野鳥の会・怪鳥
78
(2025-77)【図書館本-58】絶海の孤島、南硫黄島。本州から南に1200km、その開闢以来人類が2度しか登頂したことのない、原生の生態系が残る奇跡の島。その南硫黄島で2007年と2017年の二度にわたって行われた調査活動に参加した著者の貴重な記録。いつものおふざけオヤジギャグも今回はちょっと控えめ、真面目半分、おふざけ半分な一冊。灼熱の太陽に照らされ、崩れ落ちる絶壁を登攀しながらの野鳥調査。アカアシカツオドリの国内初の集団営巣を発見したり学術的にも面白い本。五つ星です!★★★★★2025/05/30
ホークス
53
2023年刊。南硫黄島は人の上陸を禁じている稀有な場所。鳥類学者の著者は生物調査隊として訪れた。標高900mの島は見事なアポロチョコの形。落石や転落に怯えながらの登攀と調査。全ての行動が冒険になる。上部の疎林には海鳥の巣穴が多数。人が来れば駆逐されてしまう希少な鳥たちが生き延びている。10年後の再調査では、地形の変化に従って各種の分布も変わっていた。人がいなくても変化は起こる。種の絶滅に対して、人のなし得る誠実さとは何だろう(そんな物があるのならば)。著者はどんな時も自虐や皮肉で笑わせる。その気持ちが偉い2024/05/07
NADIA
48
鳥類学者の川上先生が絶海の無人島・南硫黄島にその他の研究者とチームを組んで調査研究と冒険の旅へ出発ー!! 人の痕跡をなるべく残さぬように進める研究滞在は大変だが、その分大きな発見に巡り合いやすい。最初から最後まで安定の面白文体だが、今回は昭和のギャグもキョロちゃんもなかったのが少々残念かも。2025/08/04
道楽モン
43
10年に1度の南硫黄島への研究調査2回分。軽妙な文章に定評の鳥類学者である筆者の筆が絶好調で、読んでいて楽しすぎる。調査隊の使命と学術的な貴重さ、地形的な理由から人が足を踏み入れられない日本唯一の島への上陸という冒険の苦労の二本立て。タイトルに偽りなし。私の大好きなカタツムリ学者の千葉聡氏も2回ともに参加していて、やたらメガネを無くしているのが可笑しい。各分野の専門家たちが、実際に根気強く調査をしている姿が生き生きと活写され、これは後身の徒に貴重な資料となるのだろう。そして学問は継承されてゆくのだ。2023/09/07
-
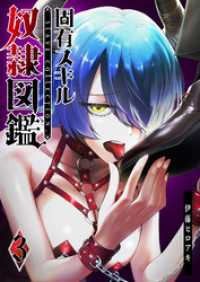
- 電子書籍
- 固有スキル「奴隷図鑑」(3) GANM…







