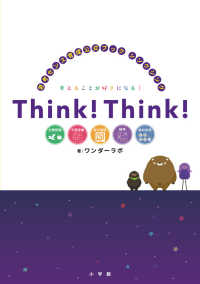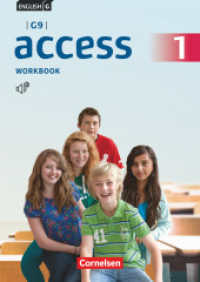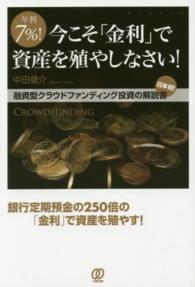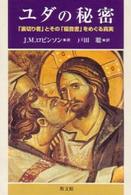出版社内容情報
本書は冷静な立場で捕鯨問題に向き合い、その論争について中立的・批判的検証を行いながら、今後の解決策を探っていく。
2014年3月31日の国際司法裁判所の判決により、日本は、南極での調査捕鯨の中止を命ぜられ今後の捕鯨政策の見直しを迫られている。
内容説明
さまざまな事柄が複雑にからむクジラ問題。いまなにが問われ、今後なにが必要か。「反捕鯨」でも「反反捕鯨」でもない新たな視点でこの問題をとらえ、今後の解決策をさぐる―
目次
第1章 クジラと人間のかかわりの歴史―日本の捕鯨は本当に日本文化なのか
第2章 捕鯨の国際管理体制と捕鯨に対する考え方
第3章 ドキュメント・捕鯨裁判
第4章 判決後
第5章 日本の新捕獲調査計画をめぐる攻防
第6章 捕鯨裁判が映しだす日本社会―その教訓を生かすためにはどうしていくべきか
著者等紹介
石井敦[イシイアツシ]
東北大学東北アジア研究センター准教授。筑波大学経営・政策科学研究科修士課程修了(修士・経済学)。筑波大学社会工学研究科博士後期課程中途退学。国立環境研究所NIESアシスタントフェローを経て、2004年より現職。専門は国際政治学、科学技術社会学。捕鯨問題のみならず、マグロ関連、大気汚染関連などさまざまな国際的な問題に対して学術的貢献と政策提言を同時並行で行うことができる研究を追求している
真田康弘[サナダヤスヒロ]
早稲田大学地域・地域間研究機構客員次席研究員・研究院客員講師(法政大学大原社会問題研究所客員研究員兼任)。神戸大学国際協力研究科博士課程前期課程修了(修士・政治学)。同研究科博士課程後期課程修了(博士・政治学)。大阪大学大学教育実践センター非常勤講師、東京工業大学社会理工学研究科産学官連携研究員、法政大学サステイナビリティ研究教育機構リサーチ・アドミニストレータを経て、2014年より現職。専門は政治学、国際政治史、国際関係論、環境政策論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
速水こもみち
nob
arnie ozawa