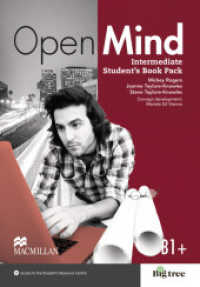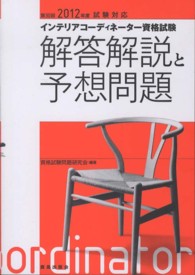内容説明
ホモ・ミュータンス―それは作りかえるヒト、の意である。人類は、遺伝子の存在を知るはるか前から、そうと知らずに、遺伝子にさまざまな操作を加えて、私たちに都合のよい、「新たな」生命を育んできた。トウモロコシ、蚕、猫、そしてまたリンゴも例外ではない。果たしてそこに「限度」はあるのか…。
目次
第1章 人間と愛犬タッツィとトウモロコシ
第2章 マルチコーリス・マニアと蚕、そして、世界初の幹線路
第3章 ライオンと猫、小さくなった猫とネズミ
第4章 天上の山々と放牧地のリンゴ
著者等紹介
ハベル,スー[ハベル,スー][Hubbell,Sue]
1935年、アメリカのミシガン州に生まれる。ミシガン大学動物学部を卒業したのち、図書館司書などを経て、最初の夫とともに、ミズーリ州オザーク山地で養蜂業をはじめる。そのかたわら科学ライターとしても活躍。のちに活動の拠点をメイン州に移し、現在に至っている
矢沢聖子[ヤザワセイコ]
翻訳家。神戸市出身。津田塾大学学芸部卒業
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
たなか
0
人類が宇宙船で連れ去られて、5,000年後に地球に戻ってきたら、猫は存在しているでしょうか…。遺伝子がテーマというと、難しく読みにくそうだけど、分かりやすい例えや、面白い経験談を交えて、とても軽い読み口でした。2017/11/14
ぴょんpyon
0
人類が何千年も前からおこなってきた育種、つまり、より好ましい特性を持つ生き物の系統を選抜して栽培・飼育し新しい品種を作す行為についての読み物です。筆者は遺伝子組換えのような操作は育種と同じことだろうとみなして容認する立場のようですが、そんなに軽く扱って良い問題でしょうか。育種にしろ遺伝子組換えにしろ、人間が手を加え続け、世話をし続けなければ生きていけない生物(品種)を作り出すというのは脅威を感じます。2016/04/13
u32
0
遺伝子組み換えの是非についてはイエスとは言い難いけど、ワインを扱っていて無農薬、有機栽培、ビオディナミ、なんかが凄く喜ばれるのをみている。商売を考えた時に、農薬も困る、コストが上がるのも困る、そんな事を言われると植物自体を強くするしかない、農業をしている人にしてみると遺伝子組み換え作物に期待をするしかない、そんな視点もあるのか、と思った。人為的淘汰や選抜クローンと遺伝子組み換えの境目ってやっぱり難しいな、と思った。あと都会の大きいネズミは本当に怖い。2015/07/02
yn_redqueen
0
「自分では芽を出せないトウモロコシ」「やけに小さくなった猫(作者は猫飼い)と、逆に大きくなったネズミ」「人間の作為と富、そして堕落の象徴となったリンゴ」などいわゆる『家畜化domesticated』された動植物をテーマにした興味深いエッセイ。カイコとリンゴに関する話のほうが気合が入っているし、家畜化に関する「社会的主張がある」本でもないので生物&農学史本としてすらすら読めてしまう…出版的に不運な星のめぐりを感じさせる本。翻訳が子供向け絵本のように丁寧なので、中~高校生にオススメしたい2011/10/04
やご
0
題とカバーの子猫の写真から愛猫家向けの本と勘違いしそうです(わたしはしました)が、内容は人間が歴史的におこなってきた「遺伝子操作」についての科学エッセイとでもいうべきもの。猫がご先祖のヤマネコに比べて小型になったのも人間の好みで選択・淘汰された結果ということです。なるほど。2005/12/14