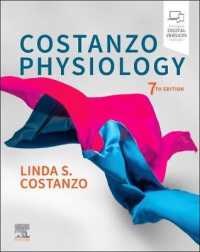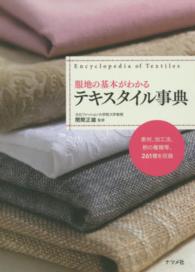内容説明
アインシュタインの美意識が相対性理論を生み、最先端の科学技術がピカソにキュビスムをもたらした。科学と芸術で二十世紀を拓いた二人の巨人の思考の軌跡をたどる。
目次
第1章 二つの世界を一つに
第2章 「かっこいい靴磨き」
第3章 「あれほど騒がれただけのことはある男の美しさ」
第4章 いかにしてピカソは『アヴィニョンの娘たち』を発見したか
第5章 ブラックとピカソは空間を探検する
第6章 驚異の年―いかにしてアインシュタインは相対性理論を発見したか
第7章 「アインシュタインにこんなことができるとは思いもよらなかった」
第8章 芸術と科学における創造力
著者等紹介
ミラー,アーサー・I.[ミラー,アーサーI.][Miller,Arthur I.]
ロンドン・ユニヴァーシティ・カレッジ科学史・科学哲学教授。『NOVA』『レイトショー』『イン・アワー・タイム』などのテレビ、ラジオ番組にも多数出演し、現代科学の歴史や哲学、認知科学、科学的創造力、科学と芸術の関係などについて多くの講演も行なう
松浦俊輔[マツウラシュンスケ]
1956年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科比較文学・比較文化専攻博士課程満期退学。名古屋工業大学助教授(科学論)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
wadaya
4
キュビスムは対象を抽象化することで本質に迫り、相対性理論は知覚を排し思考の概念化によって時間と空間の本質を捉えた。双方に共通していたものは概念を分解し、思考を再構築することで直感を得たということだろうが、そこには幾何学的な美意識があった。本書はその二つを並置する形で、実に分かりやすく書かれている。数式が苦手でも論理的な考え方に慣れている方なら読みこなせるだろう。本質さえ射抜ければ細部は放っておいたって構わない。知覚の向こう側にある前人未到の領域を垣間見る鍵がそこにある。直感は自由な精神の戯れの産物なのだ。2017/10/24
プシオ
1
ダメ。ギブアップ。僕は阿呆です。2013/01/04
たぬき
0
粗いが、ポアンカレ『科学と仮説』のインパクトがよくわかり、面白い。2023/01/02
-
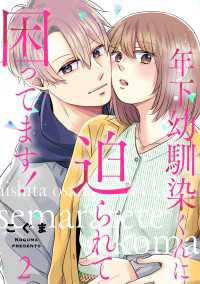
- 電子書籍
- 年下幼馴染くんに迫られて困ってます! …
-
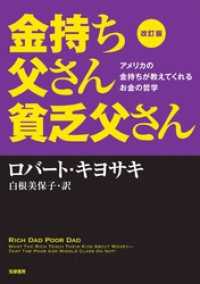
- 電子書籍
- 改訂版 金持ち父さん貧乏父さん ――ア…