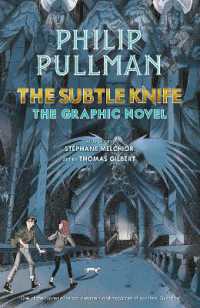出版社内容情報
ゴダール・ファンにとってはこたえられない本だろう。彼の映画作りの裏側が見えてくる。しかし、その見え方は、ゴダールの映画のように、通り一遍の見え方ではなくて、裏には裏があるという見え方だ.....。(立花隆『ぼくが読んだ面白い本・ダメな本 そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術』227頁、より)
目次
1 1950‐1958
2 その他の覚書―1960‐1974
著者等紹介
松浦寿輝[マツウラヒサキ]
1954年東京生まれ。詩人、小説家、批評家。東京大学大学院総合文化研究科教授。詩集『冬の本』(青土社、1987、高見順賞)ほか。小説『花腐し』(講談社、2000、芥川賞)、『半島』(文藝春秋、2004、読売文学賞)ほか。評論・エッセイ『平面論』(岩波書店、1994、渋沢クローデル賞)、『エッフェル塔試論』(筑摩書房、1995、吉田秀和賞)、『折口信夫論』(太田出版、1995、三島由紀夫賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
めしいらず
55
著者は己が映画をシネマトグラフと呼び、一般的な映画をシネマと呼んで相違を強調する。彼のシネマトグラフは純粋映画と思えば判り易い。映画史に於いて極めてユニークなその手法。それは徹底した無駄の排除、最小限の要素だけ繋いだモンタージュにある。俳優的演技を過剰と嫌い素人のみを起用。感情表現は失われ映るままの事実が浮上。徹底して「真実味」は除かれ「真実」だけが残る。頻出するクローズアップはその外側を想像させる。つまり私達は映画への積極的参加を促され、私達の中で映画は完成するのだ。ストイックさが彼を孤高の存在にする。2018/03/05
兎乃
33
残された長篇13作品のうち、スクリーンで観る機会はないと思っていた『白夜』が 35mmニュープリントで上映と聞き 映画館に駆け込んだ2012年12月。至福。ブレッソンの映像は詩でした。(詩という文字に ウカウカした印象を持つ人がもしいるのなら 哲学とか掟とか律法とかに言い換えてもいい。けれど、詩。詩です。)自己の判断において 普遍的な規準となる言葉が記されたこの本は、道標かもしれません。『鉄のごとき掟を鋳造して自分に課すこと。たとえそれに従うためであれ、あるいはどうにか苦労してそれに背くためであれ。』2014/03/23
らぱん
32
ブレッソンの思索や思考の断片で、ほぼ求道者のようだ。表現者としての役割は、世界に対してどのように向かい働きかけまた変えていけるかであり、その実践的で普遍的な考察を削ぎ落した言葉で著している。真の美とは創造されるものではなく、それは既に存在するものであり、見い出し捉え差し出すことが表現である。倫理的で禁欲的な姿勢から窺えるのは逆説的に官能になる。ブレッソンの映像作品を観たときに自分が感じた緊張感の正体など、感覚的に捉えていたものを論理的に確認した。徹底的に夾雑物を排除し最後に残るものが真実だということか。2019/06/15
しゅん
14
これは、手元に持っていて、ブレッソンの映画(彼自身の定義に従えばシネマトグラフ)、あるいはその他無数の映画を観るのと並行して、何度も読み返すのが適切な読み方だと思う。「俳優」ではなく「モデル」と呼ぶブレッソン文法、「スター・システム」がどれだけ映画の可能性から遠ざかるかを繰り返し指摘するところ、ドライヤー『裁かるるジャンヌ』の顔に対する批判的言及などは一読しても十分面白いけど、アフォリズムめいたメモの集積を充実させるには、やっぱりブレッソンの映画と照らし合わせるしかない。『ジャンヌダルク裁判』劇場で観たい2022/05/19
ふしぎ
6
ブレッソンの映画における感覚的なものを言葉で受け取れるというか、その方法を少し知れるというか、そういう本だと思った。ブレッソンとベルイマンは似ているような気がする。2016/07/30
-

- 電子書籍
- 傾国のカルマ 29 UPコミック