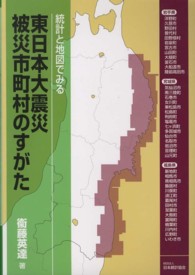内容説明
18世紀末、イギリスで発明された「パノラマ」は、巨大な装置と見る者を幻惑するさまざまな仕掛けでヨーロッパ中を熱狂させた。フランス気鋭の小説家・評論家が栄光につつまれた歴史を展望し、「イメージの魅惑」の核心にふれる。
目次
1 歴史篇(ロンドンのパノラマ―レスター・スクエアからコロシアムへ;パリのパノラマ―プレヴォーからラングロワまで;1870年までの、ドイツ、スイス、アメリカにおけるパノラマ ほか)
2 理論篇(前史;支持者と誹謗者―理想的な風景の問題;表象/錯覚―額縁の倫理 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
misui
6
18世紀末に誕生し19世紀を通して人気を博した「パノラマ」の歴史、その理論や問題点を概観する。施設としても面白いが現象としてのパノラマ…パノプティコンや文学など諸分野において現れた「全知全視」の欲望についてが興味深い。それは時間と距離を越えて全てを把握したいという欲望であり、現在に至ってはすでに一般化している。また、訳者あとがきで触れられているリアリズムとの関連も少し気になった。2016/02/18
wasabi
0
読みたかったパノプティコンの話はラストにちょろっと。多くの民衆を楽しませながらも「こんなの本物の芸術じゃないやい」と既存の美術業界から反発を生んだあたり、現代の3D映画やゲームと同じ話がいつの時代も繰り広げられているのが分かる。映画が大衆に広まる二十世紀初頭からパノラマはあからさまに衰退するんだけど、よく考えたらディズニーランドのアトラクションだったりってほとんど同じ手法だし、現代にも名残は見れる。映画史の前史としての読み方もできたりと、色々オススメ。2015/12/13
takao
0
ふむ2025/06/23
-

- 電子書籍
- 占い師星子(2) スピリッツ女子部
-

- 和書
- 国際金融論のエッセンス