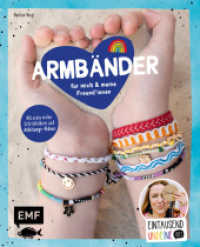内容説明
くじけないで、前へ!運命の音に導かれた、ある旅立ちの物語。書き下ろし短篇「菖蒲湯の日」を同時収録。第22回太宰治賞受賞。
著者等紹介
栗林佐知[クリバヤシサチ]
1963年札幌市生まれ。富山大学人文学部卒業。ガラス清掃、版下製作などを経て、小説を書き始める。2002年「販売機の恩返し」で第七十回小説現代新人賞を受賞。「ぴんはらり」(「峠の春に」を改題)で、第二十二回太宰治賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あつひめ
8
むかしあったがど・・・から始まる物語。大人版昔話を聞いているようだった。方言がまったり感を強調して、時々意味不明でも前後の脈絡や雰囲気で読んでしまった。菖蒲湯の日は、昔話を心のより所にして過ごす三十路の女。現在と物語がごっちゃになった女の心の中・・・歪んだ鏡で見ているような物語・・・。2009/12/14
あかんべ
4
方言で書かれている点、あえて注釈もいれず押し切っているのは、みごと。底辺の暮らしのおきみの心情や、何も無い、何もできないおきみが、希望を抱いて旅立つ姿がよかった。二つ目の話が現代のファンタジーなら、設定がストリートミュージシャンを目指す田舎娘だったら、一冊の話として面白かったのにと思った。2012/02/29
なゆ
4
第22回太宰治賞。むかしむかし、鏡てもんがなかった村があったそうな。身寄りのないおきみが庵主さまに救ってもらい、一生懸命生きるすべを模索 する姿にただただ応援したくなる。そして鏡が夫婦喧嘩のもとになったり、心の拠り所であったり、面白い小道具になっている。じゃみせんの音が素朴に描かれてて、つらい境遇のおきみを盛りたててるようなのが、いい。本当に、大人のむかしばなし、って感じ。方言も生き生きしてて、なんとはなしに好きなお話です。2011/09/29
Fumoh
1
太宰治賞受賞とのことですが、ちょっとこれは難しい……。地の文まで方言で書かれているのは、まあいいとして、女性作家にありがちなストーリーの進行が緩やか・あるいはほとんど進行しない・雰囲気や空気感で感じ取ってくれ、とするのが、実際あまりよくない。男性作家だったらロマン小説、女性作家だったら生活空気小説、これが独りよがりになる傾向が強くて失敗することが多い。どっちも「空気感」を大切にしていると思うんですけど、空気感で何かが伝わるほど読者はテレパシーに通じているわけではない。当たり前です、別の人間なんだから。2024/05/04
zikisuzuki
1
パンクロックが好きだ。世間からの疎外感が音楽への衝動となった時、その初期衝動のまま音楽への最短距離で突き進む様、それがパンクだと思っている。おきみの心は真っすぐで人の為になれるのを望み努力を惜しまない、だから人とのつながりに理不尽な目にあっても、最後の望みがある限り人を信じて止まない。そして全てを見限った時のすがすがしさはパンクロックのカタルシスに似ている。唄への激しい衝動が胸を打つ。2016/06/21
-
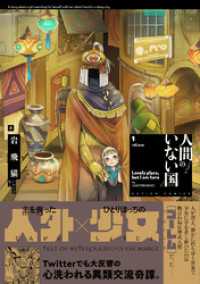
- 電子書籍
- 人間のいない国 分冊版 35 アクショ…
-

- 電子書籍
- チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、い…
-
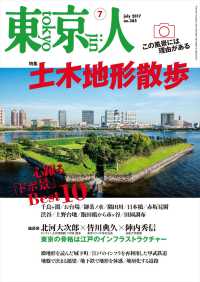
- 電子書籍
- 月刊「東京人」 2017年7月号 特集…
-

- 電子書籍
- ほしの智世 写真集 Part.16