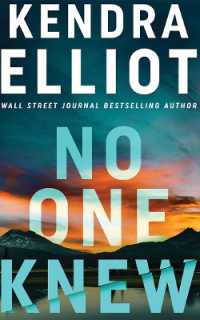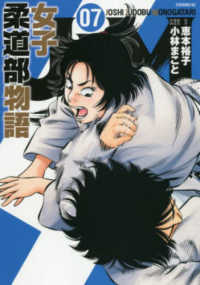出版社内容情報
海外からきた食文化を取り入れることで、日本の食は大きく進化してきた。そのなかで変わらずにいるコアな部分とは何か。私たちの食と暮らしをもう一度見直そう。
内容説明
「和食」といえば、刺身に煮もの、和えもの、ご飯に味噌汁。人気のラーメンやカレーは和食じゃないの?食をたどれば、社会の変化が見えてくる。
目次
第1章 「和食」の誕生(すしはファストフードだった―江戸時代まで;「今日もコロッケ」―明治維新がもたらしたもの;憧れのハンバーガー―敗戦後の大変革)
第2章 昭和育ちの食卓―私が食べてきたもの(ベースはすでに洋食;農村暮らしから引き継いだもの;外食大好き;メディアが描く食のかたち)
第3章 和食の今と未来(和食の何が危機なのか;学校給食は進化する;家庭科の役割)
著者等紹介
阿古真理[アコマリ]
1968年兵庫県生まれ。作家・生活史研究家。神戸女学院大学文学部を卒業後、広告制作会社を経てフリーに。1999年より東京に拠点を移し、食や女性の生き方などをテーマに執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
45
日本の食文化、特に庶民にとっての食事や料理の変遷に目を凝らすと、一般に「和食」とされる料理が「血統書付き」ではない事が分かる。時代相応の貧困や偏見、様々な偶然が重なり、生物進化の様に激しく変化してきた。著者は変化を踏まえ、「和食」と言えるものがどの様に存在し得るか考える。本書の大半は日本の食文化の歴史と新しい多面的な試みに充てられ、著者や母親の体験・実感が添えられる。「正解」は語らない。「価値あるものは何か」を考える時、「昔からこうだから」とか「新しいから」は本質ではないと改めて思わされた。2019/07/11
calaf
24
著者とはほぼ同世代という事もあってか、結構面白く読めました。なるほどと思ったことも多数。昭和時代って、その他のこともそうなのでしょうが、やはり日本人の食事にも大きな影響を与えているのですねぇ...あ、この本、奥付がない。図書館本でカバーを付けているので、そのページも一緒に挟み込んでしまっているのかな???2015/07/12
タルシル📖ヨムノスキー
22
タイトルは〝「和食」って何?〟ですが、懐石料理について解説したり、出汁(だし)についてうんちくを述べたりという、いわゆる〝THE和食〟を定義づける本ではなく、言ってみれば、「日本食文化概論」みたいな感じの本でした。「握り寿司は江戸時代のフォストフード」とか、インスタント食品、レトルト食品、デパ地下、ファミレス、イタ飯、レタスクラブ、料理の鉄人、スウィーツなんて言葉が出てくると、なんだかちょっと嬉しい。後半は学校給食や家庭科の授業の内容など、日本人の〝食〟の変遷をざっくり知るには、とてもいい本だと思います。2019/05/12
izw
19
ラーメンは和食だろうか、カレーは和食だろうか、と考えさせられる本です。日本の料理の歴史を平安時代から現代まで辿った後、自分自身の記憶、母親の生きてきた時代の料理、食文化、家庭料理、学校給食の変遷を振り返って、「和食」とは何か、今後どうなっていくかを考察しています。昭和の食を思い出しながら読め、懐かしさがこみ上げてきました。2015/10/14
Shimaneko
17
和食についてというより、一般家庭におけるごはん事情の変遷を、ざっくり駆け足で紹介したカルチャースクール的な内容。昭和生まれの世代論が興味深い。私も昔のオレンジページの煮物特集号、いまだに時々引っ張り出して見たりするもんなー。クックパッドとかのほうが簡単なのに。小林家も栗原家も、娘じゃなく息子が料理研究家を継いでる時代なわけで、たかだか数十年という短いスパンで激変した日本の食文化史と、子どもの頃の実家の台所風景にしばし思いを馳せつつ読了。2015/06/23
-

- 電子書籍
- 煌々と照る月【タテヨミ】第2話 pic…
-
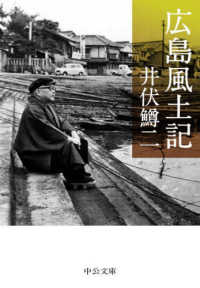
- 和書
- 広島風土記 中公文庫