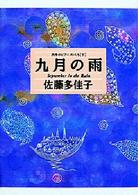出版社内容情報
日々起きる事件や出来事、問題発言をめぐって、ネットユーザーは毎日のように言い争っている。終わりのない諍いを生み出す社会やメディアのあり方を考える。
内容説明
日々起きる事件や出来事、問題発言をめぐって、ネットユーザーは毎日のように言い争っている。他人が許せないのは、対話が難しいのはなぜか。物事の見え方に違いが生まれるのはなぜなのか。背景にある社会やメディアのあり方を考える。
目次
第1章 「表現の自由」をめぐる闘争
第2章 ソーシャルメディアの曖昧さと「権力」
第3章 エコーチェンバーの崩壊と拡大する被害者意識
第4章 「不寛容な寛容社会」とマスメディア批判
第5章 二つの沈黙、二つの分断
終章 単純さと複雑さのせめぎ合い
著者等紹介
津田正太郎[ツダショウタロウ]
1973年大阪府生まれ。慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所教授。1997年慶應義塾大学法学部政治学科卒業、2001年サセックス大学大学院(Media Studies,MA)修了、2003年慶應義塾大学大学院法学研究科単位取得退学。財団法人国際通信経済研究所、法政大学社会学部教授を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
48
あとがきの大石裕教授には、2006年慶應通信SSでマスコミュニケーション論にて懐かしく思い出した。個人化が進む社会だからこそ、迷惑行為も。人それぞれを侵害する行為。主体的とみなされる他人の決定に干渉する行為が批判されやすくなる。自粛警察を事例にされている(157頁)。被害者のプライバシー保護は、企業や自治体、警察の不祥事隠蔽の名目に用いられることもあるようだ(171頁)。事件や事故で氏名が報道されるが、加害者、容疑者が後になって判明したり、迷宮入りしたりする事件もある。ネット社会の健全性とは何か? 2024/12/28
yuni
37
某アニメの内容について個人的な意見をツイートして「炎上」騒動になったメディア社会学者が自らの経験を踏まえて、SNS上の言い争いについて考察した内容。ネット上が公共性の高い場所だという意識が欠落していると、それが世間的にモラルに反することであれば、迷惑行為だと多くの人が解釈して、炎上することは火を見るより明らかである。本書では政治の話が多めだが、身近なところで言えば推し活などでも同じ価値観の人が集まる中で極端な意見を発信する人がいれば分断が発生する。ネット論争は根深い問題でこの先も無くなることはないだろう。2024/07/18
よっち
36
日々起きる事件や出来事、問題発言を巡って毎日のように言い争っているSNS。他人が許せず対話が難しいのはなぜか。自身も炎上を経験したメディア社会論者が分析する1冊。アニメの感想を書いたら炎上した実体験も踏まえながら、メッセージ解釈はいかにしてズレていくのか、同じような価値観や考え方の意見ばかりに触れやすい状況、快適な社会のパラドクスと新たな迷惑行為の発見、リスクを恐れての沈黙で多数派でなくなる皮肉、複雑なことよりも単純なことの方が伝わりやすいなど、テキストでコミュニケーションを取る難しさを改めて感じました。2024/05/30
山口透析鉄
33
これも市の図書館本で、やはり色々と示唆に富む内容でした。Twitterの匿名性に起因する極端で無責任な意見、いくらでも見れるでしょう。実際は発信者たるには色々と配慮しきれない利用者は一定いるでしょうから、いつも揉めているように見えるのかも知れません。(Xに変わって良くなった点が見えないので私も未だにTwitterと書いています) 社会の変遷との関係等の指摘もなるほどです。マスメディア不信は今に始まったことではないですが、批判する側もピンキリなので、やはり知の基礎体力はいるのでしょう。(以下コメント欄に)2025/05/05
ま
28
ネットを通じて社会を見ることで、ユーザーは日夜こちら側とあちら側に分ける境界線を引き続けているのかなという気がする。そしてそれを利用するのが激怒産業。あちら側の醜悪さをことさらにアピールして民衆を焚きつけ、分断を生じさせている…というイメージを持った。ただ分断は、権力者がさまざまな意見を封じて画一化させているのではないという意味では必ずしも悪い現象ではない。2025/02/27