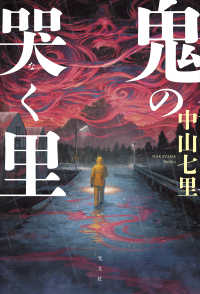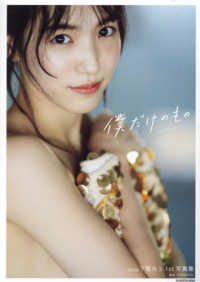出版社内容情報
さびれつつあった図書館はどのようにして日本で最も注目されるようになったのか? 鹿児島県指宿市の図書館を変えた地元女性たちの大奮闘の物語。
内容説明
鹿児島県指宿市のさびれつつあった図書館を日本で最も注目を集める施設にしたのはいちユーザーに過ぎなかった地元女性たちだった。人々をつなぐ奇跡の図書館ができるまでの物語。
目次
第1章 図書館界の憧れ、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー
第2章 新しい図書館が始まった
第3章 図書館をつくった人々
第4章 子どもたちが育つ図書館
第5章 図書館はプロの探偵
第6章 サードプレイスとしての図書館
第7章 走れ!ブックカフェ号
著者等紹介
猪谷千香[イガヤチカ]
東京生まれ。明治大学大学院博士前期課程考古学専修修了。新聞記者、ニコニコ動画のニュース編集者を経て、2013年にはハフポスト日本版の創設に関わり、国内唯一のレポーターとして活動。2017年からは弁護士ドットコムニュース記者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
64
一読、こんな素敵な図書館があるんだなあ、と実感する。言ってしまえば、鹿児島県は指宿市の二つの図書館にまつわる「そらまめの会」というNPO法人の歴史と現況ということになるだろうか。会の活動は、2021年の「ライブラリー・オブ・ザ・イヤ-」として実を結ぶ。市民に愛され出会いの場として機能する、小さな町の図書館が理想に近い形で現出するまでの、関係者のご苦労や工夫・アイデアが満載である。それはどこまでも、「そらまめの会」という、人と場があって初めて現出したのだろう。その秘密は?。メンバーが全員女性なのもその一つ?2023/04/08
とよぽん
61
猪谷千香さんの、ちくまプリマー新書というだけで必ず読もうと思った。やはり、取り上げるものが他のジャーナリストとは違う視点で、とても素敵な内容だった。小さなまち・・・指宿市でもそう表現されることに少し違和感をもったけれど、歴史をさかのぼれば小さなまちだったのだ。指定管理者、という制度が行政の丸投げっぽい印象を与えてしまいがちだが、そらまめの会の方々は指宿市と図書館を愛する素晴らしい方々で、あくなき追求心と行動力、情熱に感動した。文字通り、奇跡の図書館だった。2023/04/06
みつ
42
南九州、指宿市の図書館に指定管理制度が導入される際、寂れた図書館の再生を決意したNPO法人の話。なお「指宿市立図書館」は「指宿図書館」と「山川図書館」の2館で構成され前二者は文中使い分けているので、一応念頭に置いて読み進む。電算化、お話会の出張、駅との連携、そして最大の山場とも言えるブックカフェ号購入のためのクラウドファンディングなど、多くの取り組みが紹介される。これを実現したNPO法人「そらまめの会」のメンバーがわずか12人(全員女性)であるのは驚き。「認定司書」など高い専門性にも裏打ちされている。➡️2024/06/27
よっち
38
さびれつつあった図書館はどのようにして日本で最も注目されるようになったのか?鹿児島県指宿市の図書館を変えた地元女性たちの大奮闘の物語。電算化もしていない薄暗かった市立図書館を、学校司書などの関係者が立ち上げたNPOが指定管理者としてゼロから作り上げていった鹿児島の図書館。住民の協力も得ながら21年にその年の注目する図書館が選ばれるライブラリオブ・ザ・イヤーを受賞するまでを取材していて、その試行錯誤もいろいろな方と話し合いや助力があったからこそ成功に繋がったわけで、地に足付いた取り組みが重要なんでしょうね。2023/02/04
Nobuko Hashimoto
33
指宿のさびれかけた図書館の指定管理者となったNPOが、住民の協力も得て立て直しに成功する。その経緯も面白いのだが、第3章の指宿に図書館をつくった人々の章が非常に興味深い。戦後、農村の暮らしを向上させるために図書室をつくると農村の人々に読書熱が高まり、図書館の本で研究して花卉栽培に成功する農家の女性たちも出てくる。それを支えた県立図書館長が椋鳩十さんだったのか!/とても面白くて一気読みしたが、なぜちくまプリマーで出したのだろう。もっと人件費を出すべきという提言もあることだし、大人向け新書でもいいような。2023/01/26