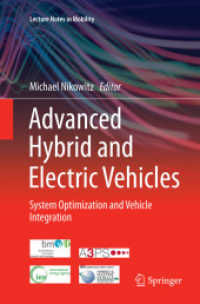出版社内容情報
心が弱っているのは「脳」の調子が悪いだけかも? ――あいまいで実体のなさそうな「心」を脳科学から捉えなおして、悩みにとらわれすぎない自分になろう。
内容説明
調子が悪いとき、「気の持ちよう」などと言われることがある。だけど心のはたらきは、実は脳が生み出す生理現象に過ぎない。あいまいで実体のなさそうな心を「脳科学」から捉えなおして、悩みにとらわれすぎない自分になろう。
目次
第1章 心ってどんなもの?
第2章 脳ってどんなもの?
第3章 心を生み出す脳のはたらき
第4章 心が病むってどういう状態?
第5章 心を守る心のはたらき
第6章 「気の持ちよう」と考えてしまうワケ
第7章 「気の持ちよう」をうまく利用する
第8章 「わたし」ってなんだろう
著者等紹介
毛内拡[モウナイヒロム]
1984年、北海道函館市生まれ。2008年、東京薬科大学生命科学部卒業。2013年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員を経て、2018年よりお茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教。同大にて生体組織機能学研究室を主宰。専門は、神経生理学、生物物理学。主な著書に『脳を司る「脳」』(講談社ブルーバックス/第37回講談社科学出版賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
morinokazedayori
20
★★★★脳も臓器の1つなので、調子のよい時も悪い時もある。意欲がわかなくなる、思考がネガティブになるなどは、調子の悪さからくるという。序盤の脳内物質の説明は咀嚼しきれなかったが、メカニズムや対処法が分かりやすく書かれていた。2024/08/14
ホシ
20
脳科学をはじめ心理学や精神分析学などの「心」に関わる事を広く浅く解説します。高校生でも読めると思うので素人の私でもやさしく読めました。最近は脳科学がマイブームなので関連本を何冊か読みましたが、その中では本書が最も初学者向き。とはいえ内容が浅い訳ではなく、森田療法なんかは始めて具体的な中身を知りました。また、これまで読み知った脳に関する知識のおさらいになった一冊かな。メンタルを病みやすい時代。胃もたれや筋肉痛といった時はそれぞれを労るのと同じように「脳を労る」という習慣が広まることを願うばかりです。2023/02/17
どら猫さとっち
9
なんでも気の持ちようとか、心が折れるとか、今までそういう言葉に違和感を抱いてきた。それを、本書でそうではないんだということを思い知らされた。脳の仕組みによって、体調が良くなったり、悪くなったりする、なぜ鬱になるのか、自己肯定感を得るにはなど、脳科学から提唱する。精神力や根性論と信じて振りかざして、発破をかける人たちに、本書を読んでおきたい。2022/11/20
大先生
8
【「心」とは脳という臓器のはたらきの一部である】という前提から脳内で分泌される物質等が心にどのような影響を与えるのか等について分かりやすく解説した本です。【心は「気の持ちよう」でどうにでもなるという俗諺はいい加減なものですよ!でも、それを上手く活用することもできるかも】ということを丁寧に解説した本とも言えます。メンタル不調のときは、①成功体験を共有する仲間と未来を語る、②ひとり旅、③瞑想=今この瞬間を意識する、④あるがままを受け入れる(森田療法)⑤認知を可視化するといいそうです。2023/07/04
乱読家 護る会支持!
5
「悲しいから泣くのか」あるいは「泣くから悲しい」のか、心と脳(身体)の関係は、まだわからないそうです。 僕はどちらでもあるかなぁと思います。 『我々の心(意思)は、感情をコントロール出来ないし、身体もコントロール出来るのは筋肉だけ。 ならば、出来ないこと(感情のコントロールなど)はあきらめて、出来ること(行動)を変えよう。行動すれは、感情は後から変わってくる。 いや、そもそも感情はそのまま受け入れればよい。』 などと考えました。2023/06/27
-

- 和書
- 明解量子重力理論入門