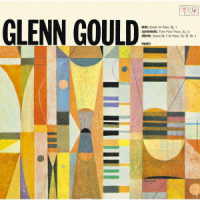出版社内容情報
地球的課題を身近な将来の出来事として捉え、ひとりひとりが社会問題の解決や持続可能な開発に主体的に貢献するために、まずは知ることから始めよう。
内容説明
サハラ砂漠で進む「巨大な緑の壁」計画とは?地球と人類について考える地理だからこそ環境問題だけでなく、人権、貧困、経済成長…全てが学べる!
目次
第1章 環境問題は国境を越える(異常気象が頻発するオーストラリア;深刻な大気汚染の原因 ほか)
第2章 人権を守るとはどういうことか(日本はどこまで女性の地位が低いのか;「最貧国」から卒業するバングラデシュの光と影 ほか)
第3章 経済成長は世界に平和をもたらすのか?(中東産油国は豊かなのか;コンフリクトミネラルズが助長する紛争 ほか)
著者等紹介
宇野仙[ウノタケル]
1978年1月20日、北海道旭川市生まれ。慶応義塾大学商学部卒。駿台予備学校地理科講師。元Z会東大進学教室講師。元河合塾地理科講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 哲学の世界 時間・運命・人生のパラドク…
-
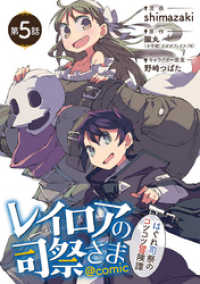
- 電子書籍
- レイロアの司祭さま~はぐれ司祭のコツコ…