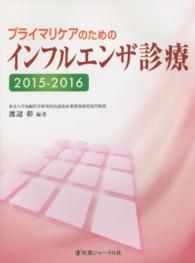出版社内容情報
日本古来の神と大陸伝来の仏、両方の信仰を融合する神仏習合理論。前近代の宗教史的中核にして日本文化の基盤をなす世界観を読む。解説 末木文美士
内容説明
日本古来の神々は仏が姿をとったものであるとする神仏習合の思想、本地垂迹説。しかしそれは、仏教と神道が融合したのみならず、道教・陰陽道・儒教など中国思想が流入し、さらに歴史的人物をも取り込んで、複雑な多神教的様相を呈するまでに発展したものである。この日本独自の世界観は、朝廷や貴族の政治理念に影響する一方で、庶民の日常生活にも浸透し、数々の文芸・美術作品を残した。前近代の宗教史的中核に位置し、日本文化の基盤へと広く深く根を張る世界観を総合的に読み解いた名著。
目次
1 大陸における本地垂迹説の起源と仏教の習合的発展
2 仏教の日本伝来初期における歴史的情勢
3 律令国家完成期に至る神仏両思想と陰陽道の関係
4 奈良朝における神仏習合の進展
5 八幡神の習合的成長
6 御霊会の発生と成立
7 祇園社の御霊神的発展
8 天満天神信仰の成立と御霊思潮の変転
9 金剛蔵王菩薩と金峯山信仰
10 熊野三山の信仰
11 念仏諸宗と神祇信仰
12 日蓮宗および禅宗と神祇信仰
13 縁起譚と習合文芸
14 神影図と習合曼荼羅
15 天台の神道
16 真言の神道
17 卜部家の神道
18 本地垂迹説の終末
著者等紹介
村山修一[ムラヤマシュウイチ]
1914‐2010年。大阪生まれ。京都大学文学部史学科卒業、博士課程修了。大阪女子大学名誉教授。専攻、中世史、民間信仰史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
ネギっ子gen
やいっち
わ!
SOLVEIG
-

- 電子書籍
- 蒼穹の剣【タテヨミ】第77話 picc…
-
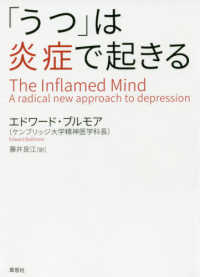
- 和書
- 「うつ」は炎症で起きる