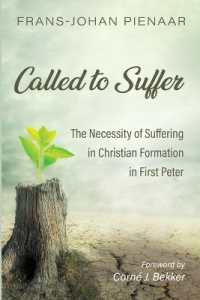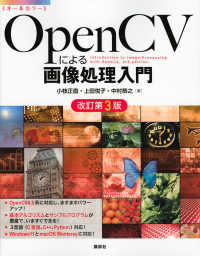出版社内容情報
邯鄲古城、長安城、洛陽城、大都城など、中国の城郭都市の構造とその機能の変遷を、史料・考古資料をもとに紹介する類のない入門書。解説 角道亮介
内容説明
ときに長さ数十キロ・高さ十メートルを超える城壁で都市全体を囲んだ、中国の巨大な城郭都市。はやくは四千年以上前に作られ、一部戦乱期を経て継承・増改築された数々の城壁は地表・地中にその跡を遺し、現在も発掘調査が行われている。本書は、殷から清までのおもな城郭都市の構造を、史料と考古資料をもとに網羅的に紹介する類のない入門書。長安城、洛陽城、北京城など皇帝の住む都城から、地方行政の中心である州城・県城まで。城郭都市の発生、その構造の変遷から浮かび上がるのは、政治や戦争、人々の暮らしの変化だ。豊富な図版とともにあまたの城壁を渡り歩く、ダイナミックな中国都市史。
目次
第1章 新石器時代の城郭遺址
第2章 殷周時代の城郭
第3章 春秋・戦国時代の城郭
第4章 秦漢時代の城郭都市
第5章 魏晋南北朝時代の城郭都市
第6章 隋唐時代の城郭都市
第7章 宋代の城郭都市
第8章 遼・金・元時代の城郭都市
第9章 明清時代の城郭都市
著者等紹介
愛宕元[オタギハジメ]
1943‐2012年。京都大学大学院文学研究科博士課程(東洋史学専攻)中退。文学博士。京都大学名誉教授、元・帝京大学教授。専門は中国史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。