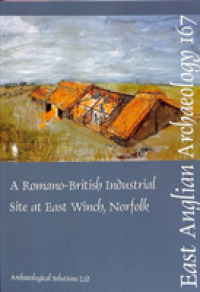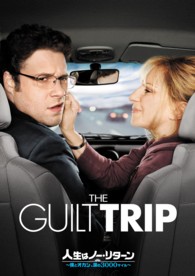出版社内容情報
極北のインディアンたちは子育てを「あそび」とし、性別や血縁に関係なく楽しんだ。親子、子どもの姿をいきいきと豊かに描いた名著。 解説 奥野克巳
===
極北の雪原に生きる狩猟民ヘヤー・インディアンたちにとって、子育ては「あそび」であり日々のこの上ない楽しみだった。ジャカルタの裏町に住むイスラム教徒は、子どもの喧嘩を「本人同士のビジネス」と言って止めずに眺めていた。本書は、環境や習慣が異なる社会における親子、子どものありかたをいきいきと描き出した文化人類学的エッセイである。どのような社会に生まれても子どもは幅広い可能性を内包しながら成長していくことが、みずからのフィールドワーク経験をもとにつづられる。鮮彩なエピソードの数々が胸を打つ名著。
===
成長の道はひとつではない
子どもの豊かな可能性をひらく名著
===
内容説明
極北の雪原に生きる狩猟民ヘヤー・インディアンたちは子育てを「あそび」として性別、血縁に関係なく楽しむ。ジャカルタの裏町に住むイスラム教徒は、子どもの喧嘩を「本人同士のビジネス」と言って止めない。本書は、環境や習慣が異なる社会における親子、子どものありかたをいきいきと描き出した文化人類学的エッセイである。どのような社会に生まれても子どもは幅広い可能性を内包しながら成長していくことが、みずからのフィールドワーク経験をもとにつづられる。鮮彩なエピソードの数々が胸を打つ名著。
目次
切ることと創ること
親の仕事を知らない子どもたち
からだとつきあう
一人で生きること
けんかをどうとめるか
親子のつながり
あそび仲間のこと
「あそび」としての子育て
「親にならない」という決断
自然の中で作るおもちゃ〔ほか〕
著者等紹介
原ひろ子[ハラヒロコ]
1934‐2019年。東京大学教養学部卒業。ブリンマー大学大学院修了。文化人類学、ジェンダー研究が専門。拓殖大学助教授、法政大学助教授、お茶の水女子大学名誉教授などを歴任した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tsu55
塩崎ツトム
ほし
ぷら
kuroma831
-
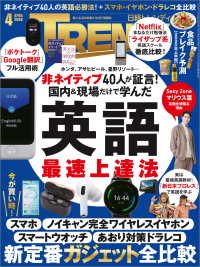
- 電子書籍
- 日経トレンディ 2020年4月号