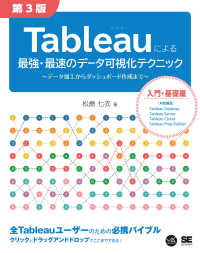出版社内容情報
ゼロの発明だけでなく、数表記法、平方根の近似公式、順列組み合せ等大きな足跡を残してきたインドの数学を古代から16世紀まで丹念に辿る。
内容説明
サンスクリット文化圏の数学は、多様性と創造性に溢れ、数学史においても大きな足跡を残してきた。「ゼロの発明」はとりわけ有名であるが、それにとどまらない。本書は、ヴェーダ祭式の祭場設営に由来する最古層の幾何学に始まり、ジャイナ教徒の数学と哲学・世界観との関係、数学と天文学、7世紀以降のアルゴリズム数学と代数の確立など、各時代に開花した数学を概観し、その発展の過程を探る。終章では、三角関数、ホロスコープ占星術、筆算法、和算などのトピックを通して、インドと他文化圏との数学の伝播を考える。
目次
第1章 数表記法とゼロの発明
第2章 シュルバスートラ(祭壇の数学)
第3章 社会と数学
第4章 ジャイナ教徒の数学
第5章 アールヤバタの数学
第6章 インド数学の基本的枠組みの成立
第7章 その後の発展
第8章 文化交流と数学
著者等紹介
林隆夫[ハヤシタカオ]
1949年新潟県生まれ。専門は、数学史、科学史、インド学。東北大学理学部数学科卒。京都大学大学院文学研究科梵語學梵文学専攻博士課程修了。ブラウン大学大学院数学史専攻Ph.D.同志社大学名誉教授。フランス学士院サロモン・レイナー基金賞、日本数学会第一回出版賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Steppenwolf
0
私には評価する資格ない.インド人名など耳慣れぬ題名や人名で内容を頭に入れることができなかった.サンスクリット語を少しでも馴染んでいたら話は別だったかもしれない.ケララ州の数学や三角関数の級数展開の話などを詳しく知りたく思って読み始めたもののサラッと触れられるのみのように感じた.インド料理店にいってインドの数学のことを聞いてみたいという欲求もあるが,インドは広大なので北と南,東と西で文化的に違うと思う.著者は,数学文化という雑誌にもゼロのことを寄稿されていたのでそちらにも目を通してみたい.2023/06/13
ミント
0
★★★ サンスクリット文化圏の数学の歴史。2020/11/12
-
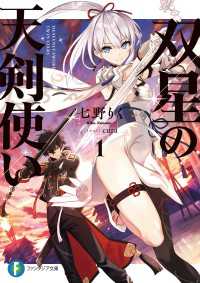
- 電子書籍
- 双星の天剣使い1 富士見ファンタジア文庫