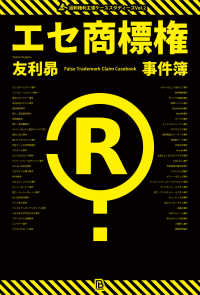出版社内容情報
植民地政策のもと設立された朝鮮銀行。その銀行券等の発行により、日本は内地経済破綻を防ぎつつ軍費調達ができた。隠れた実態を描く。解説 板谷敏彦
内容説明
日本の植民地政策のもとに設立された朝鮮銀行。その営業実態は軍部の大陸侵攻とも深くかかわっており、とりわけ日中戦争期以後の日本の軍費調達に重要な役割を担っていた。国力の乏しかった日本は、日銀券を増発するかわりに、中国連合準備銀行との預け合など「金融上のやり口」を駆使して、植民地通貨を発行した。これにより内地経済の崩壊を防ぎつつ戦争の継続が可能になったのである。朝鮮銀行関係の極秘資料にも精通していた著者が、歴史に隠れたその実態を緻密に描きだす。
目次
第一国立銀行の朝鮮進出
韓国併合を進める日本
朝鮮銀行、満州へ進出
第一次世界大戦と中国借款
シベリア出兵と鮮銀券の“シベリア出陣”
ロマノフ金荷の買い取り
金融恐慌時の朝鮮銀行
満州事変と中国の幣制改革
日中戦争と戦費の調達
太平洋戦争下の朝鮮銀行
終戦と朝鮮銀行の閉鎖
韓国銀行発足と朝鮮戦争
著者等紹介
多田井喜生[タタイヨシオ]
1939年、長野県生まれ。東京大学経済学部卒、朝鮮銀行の第二会社・日本不動産銀行(日本債券信用銀行)に入行。日債銀総合研究所を経て、財団法人日本総合研究所参与。2018年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
21
戦争を進める上で日本がどのように軍事資金を流通させるスキームを組み立てたか、そして、あれだけ莫大な軍票を発行しながら戦争中に本国でハイパーインフレが起きなかった理由が分かる面白い一冊。時系列順で書かれており、朝鮮銀行の業務内容の拡大、変化の様子も分かりやすい。見方によっては日本は円を守るために緻密なファイナンスをしていたとも考えられるが、実際に中国連銀円が流通していた中国戦線では経済が混乱したから日本軍の占領政策は成功する見込みがとても薄かったとも読めるので興味深かったです。2020/11/15
MUNEKAZ
18
これは面白い。金融から見た日本の大陸侵略といった趣で、朝鮮銀行を軸に東アジアに巨大な通貨圏を築こうとした帝国日本の企みが描かれる。日本が朝鮮に作った朝鮮銀行は独自に通貨発行が出来、鮮銀券は内地の経済と植民地の経済の緩衝材として働いた。それは戦時中の内地のインフレを抑制し、日本経済を守ったと。戦後、官僚が「昔の人はえらかった」と述懐するのが印象的。ただ中国国内の混乱やそもそも日本経済に体力がなかったせいもあり、東アジアを円ブロックにする構想は失敗する。「戦争は紙でするもの」というギラついた言葉が全てである。2023/05/23
筑紫の國造
7
日本の大陸進を強力に推進した、朝鮮銀行の通史。政治や軍事ばかりが注目される近代日本史だが、通貨・金融もまた密接な関係があることを分からせてくれる。著者は元銀行マンであり、専門的な知識が必要な当該分野の叙述にも適任だったのだろう。ただ、金融や通貨という分野の性質上、やはり専門知識がないときちんと理解するのは難しい。通貨障壁論については概ね理解できたが、もう一つの大事な概念である「預け合い」については理解できたようなできないような微妙なところである。また、専門用語もかなり多様されているので注意が必要。2025/01/21
かやは
4
すばらしい労作。お金の流れから見た戦前戦中というのは新鮮でした。▽ロシア革命とシベリア出兵のどさくさで出てきた大量の金塊を積んで満州の鉄路を爆進する特別列車のわくわく感w▽それにしても、ネットの無い時代に「日本円→米ドル→中国元→日本軍票→日本円」と両替してくだけで100円が182円になるという錬金術を発見して実際にやっていく行動力ですよ。たくましき庶民の力(と美化してはいけないw)▽自分たちのカネを使わせたい日本側とたくましき庶民との戦いの歴史でしたね。最後滅茶苦茶になりましたが……。2020/10/15
micheldujapon
3
朝鮮銀行の戦史。如何に通貨制度が国家統治に重要か改めて思い知る。メキシコ銀貨が東アジアで流通していた話、金本位(実態は金本位の円を基軸とした円本位)に切り替えることで銀本位の中国法幣を駆逐した話、第一銀行が朝鮮半島の発券銀行であった時期があったこと、朝鮮銀行が満州で大きな業務・役割を担っていた(大陸の業務の方が大きかった時期もある)こと、朝鮮戦争中に北朝鮮軍がソウルを占拠したときに韓国銀行から未発行銀行券と原盤を奪取して通貨を濫発した話、などなど非常に興味深い事実がたくさん。とても勉強になった。2020/10/16