出版社内容情報
一冊の本にはドラマがある。古書店を舞台に繰り広げられる人間模様!いい話、怖い話などをセレクトしたオリジナル・アンソロジー。解説 南陀楼綾繁
内容説明
古本屋店主にして作家となった出久根達郎。その古本小説のなかから傑作を選び出したアンソロジー。少年時代の本との出会い、下町の古本屋での修業時代、独立後の苦労など、著者自身の体験を作品化したもの。本に憑りつかれた人々の妄執の凄まじさ、一冊の本に込められた思い、人と本が織りなす様々な人生模様を描いた作品23編を収録。オリジナル・アンソロジー。
著者等紹介
出久根達郎[デクネタツロウ]
1944年茨城県生まれ。73年から東京都杉並区で古書店・芳雅堂(現在は閉店)を営む傍ら、文筆活動に入る。92年『本のお口よごしですが』で講談社エッセイ賞、93年『佃島ふたり書房』で直木賞を受賞する。2015年には『短篇集半分コ』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
102
出久根さんの古本屋の関する小説をまとめたもので、今までの作品集のなかからピックアップされたものが多いように感じました。やはり読んでいて懐かしいものが多く楽しめました。最近は、昔ながらの古本屋はなくなってしまい、残念な感じがします。小説のようなあるいはエッセイのような感じのものが多く、現実なのか虚構なのかわからなくなってしまいます。それが出久根さんの意図しているところなのかもしれません。2024/03/08
遥かなる想い
96
昔懐かし古本屋に纏わる物語である。 昭和の本好きの人々の語らいが ひどく 心地良い。学生時代の黴臭い古本屋の 匂いが蘇る。何でもない些細な出来事を 昭和の色で描いた 古本屋の短編集だった。 2024/08/30
tamami
62
溜まりに溜まった本の終活を、などと考えていたら著者の名前に引っ掛かるものを感じ手に取る。著者出久根達郎さんの、古本に題を取った小説集。80年代、90年代の作品が多く、昭和の雰囲気を強く漂わせている。単に古書店の店主とお客というだけではなく、様々な人情の機微を散りばめて物語は展開する。意外な結末もあり、少し筋が見えにくい小説もあり、紙の本がまだ本として存在感を示していた時代の、幻灯の映像を見ているような思いに囚われる。出典元の作品集に著者の『漱石を売る』が長年の積ん読本の中にあり、心に懸かった訳が知られた。2023/12/29
niisun
25
出久根達郎さんの本は『御書物同心日記』くらいしか読んだことがありませんが、古書店の店主にして作家というのは存じ上げていたので、この『古本屋小説集』は楽しみでした。中学卒業後に集団就職で月島の古書店に勤めた後に独立して中野で古書店「芳雅堂」を構えた著者の実体験を基に描かれる小編。舞台となる古書店、登場する人物、時代の様相など、ディテールも鮮明で、その情景がありありと浮かぶ一方で、どこか夢物語のように儚い一面もあり、とても魅力的です。亡くなった方と本の結びつきを描いた“最後の本”の四編が特に印象に残りました。2024/06/11
pirokichi
25
中学卒業後集団就職で築地の古書店に就職。その後29歳で独立し、高円寺で古本屋を開業。そのかたわら作家デビュー。本書はそんな出久根達郎さんの、古本屋に纏わる私小説のような随筆のような作品集。著者は幼少期より本が大好きで、理屈抜きで古本屋という商売が好き。なので、本と店を訪れる人たちへの愛情が作品から感じられるのがいい。当たり前だけど、一冊一冊の本には物語があり、人それぞれの思いが付着しているんだなあ。「饅頭本」なんて知らなかった。全23篇の中では『背広』、『東京の蟻』、『雪』、『無明の蝶』が特に好きだった。2023/12/14
-

- 電子書籍
- お飾り王妃になったので、こっそり働きに…
-

- 電子書籍
- ヘテロゲニア リンギスティコ ~異種族…
-
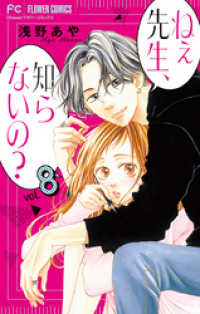
- 電子書籍
- ねぇ先生、知らないの?【マイクロ】(8…
-
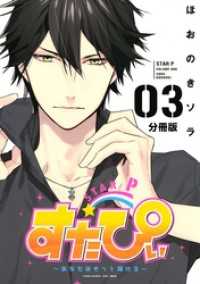
- 電子書籍
- すたぴぃ~あなたはもっと輝ける~ 分冊…
-

- 電子書籍
- ル・ボラン2016年10月号




