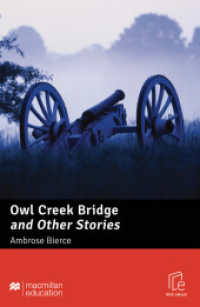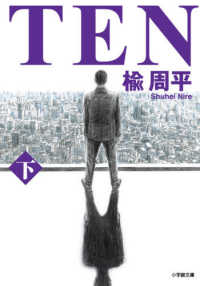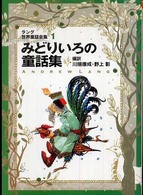出版社内容情報
ミスをなくすための校閲。本の声である書体の制作。もちろん紙も必要だ。本を支えるプロに仕事の話を聞きにいった、情熱のノンフィクション。
内容説明
ミスを無くすためだけではない校閲。本に似合った衣装を着せる装幀。紙を本にする製本。本の声ともいえる書体。もちろん紙がなければ本はできない。そういった「本づくり」の舞台裏を私たちはあまり知らない。本を支えるプロフェッショナルの仕事に対する熱い想いを届けるために、彼らの言葉を聞きにいく。読めばきっと、見方がぐっと変わり、本が愛おしくなる情熱のノンフィクション。形のある本を愛するすべての人へ。
目次
第1章 活字は本の声である
第2章 ドイツで学んだ製本の技
第3章 六畳の活版印刷屋
第4章 校閲はゲラで語る
第5章 すべての本は紙だった
第6章 装幀は細部に宿る
第7章 海外の本の架け橋
第8章 子供の本を大人が書く
著者等紹介
稲泉連[イナイズミレン]
1979年、東京生まれ。早稲田大学第二文学部卒。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で大宅賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
90
文庫化を機に手に取る。「本づくり」に関わる「作り手」たちを描いた味わい深いルポである。活字書体の製作者、製本マイスター、活版印刷屋、校正・校閲者、製紙業者、装幀者、海外本の紹介者、子供の本の制作者が登場し、それぞれのプロの凄さに圧倒される。私は、中でも、新潮社のカリスマ校閲者・矢彦孝彦さんの話に感動した。塩野七生先生が「会社を辞めても私の本を続けてみてほしい」と仰るだけのことはある。著者は「ぼくは「本」という形あるものが好きだ」と言う。そう、本は、多くの職人たちの技が結晶した「形」なんだ。データじゃない。2021/04/01
佐島楓
82
校閲、装丁、活版印刷といった紙の本に関わる仕事に就いている方々のルポ。ひとりひとりにドラマがあり、分野ごとの苦労、超絶技巧があり、培われた矜持がある。こうやって連綿と受け継がれてきた技術があるから、今日わたしたちは本を読める。本好きにはおすすめの作品。2022/01/07
ネギっ子gen
79
【一冊の本には、様々な「本をつくる人々」が関わっている】装丁、印刷、製本など本の製作を支えているプロを訪ね、仕事に対する姿勢や思いを聞いた本。単行本は2017年。本文庫の方は2020年刊。<彼らに共通していたのは、仕事に対してとことん向き合おうとするプロフェッショナルな姿勢であったように思う。それがたとえ失われつつある世界であったとしても、彼らは自らが抱え、大切にしている世界に工夫を加え、新しい世界を切り拓こうとしてきた人たちであった。そこに浮かび上がるのは、一つの豊饒な“ものづくり”の世界だった>と。⇒2025/01/27
けんとまん1007
66
本は読む方だと思う。いつ頃からだろう・・やはり、大学生の頃からだったかと思うが、本は身近にあるもので、無いことが考えにくくなっていた。結婚し家族が増えてからも同じで、今に至っている。そんな本に携わる人たちの思い・姿勢が伝わってくる。本は、やはり物理的な本がいい。手触り・重さ・匂いなどなど、五感に響くものがある。自分にとっては、生活の大切な部分を占めているし、それは、これからも変わらない。1冊の本の存在は、とてもありがたいものだ。2025/02/10
バイクやろうpart2
56
稲泉連さん作品一作目です。ほんのひと時、豊かな時間をもらう『本』、これまで、当たり前に書店に並んだ本を手にするだけでした。この本に出会い、『本づくり』の舞台裏に携る方々の真摯な姿、そして奥の深い仕事から発せられる心に響く響く言葉に感動しました。毎日、『当たり前に手にしている本』を新たな目線で眺める良い機会になりました。オススメです。2021/01/24
-
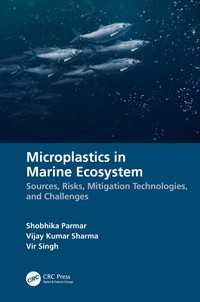
- 洋書電子書籍
- Microplastics in Ma…
-

- 電子書籍
- WAGONIST 2019年 5月号