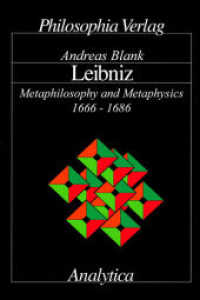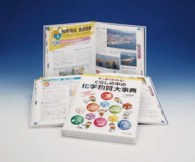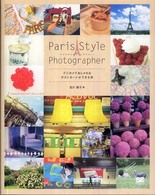内容説明
明治末から昭和初頭に熱いブームが起こった「怪談」。時代が激動する最中、不可思議な話を持ち寄り語る百物語怪談会(=怪談ライブ)に没頭したのは、泉鏡花を筆頭に柳田國男、芥川龍之介、喜多村緑郎、鏑木清方ほか一流の文化人たちだった。紅葉門下時代~晩年迄の鏡花の活動を鍵として当時の文化・世相を解き明かしつつ、文豪たちの怪談実話も多数収録。前代未聞の怪談評論×アンソロジー!
目次
第1章 硯友社の怪談(尾崎紅葉の怪談;江見水蔭の怪談 ほか)
第2章 百物語の新時代(浅井了意の怪談;山本笑月の怪談会ルポ ほか)
第3章 われらが青春の怪談会(幻覚の実験(柳田國男)
幼い頃の記憶(泉鏡花) ほか)
第4章 怪談まつりの光と影(怪談の会と人;怪談が生む怪談(鈴木鼓村) ほか)
第5章 おばけずきの絆(百物語―芥川龍之介『椒図志異』より;河童―芥川龍之介『椒図志異』より ほか)
著者等紹介
東雅夫[ヒガシマサオ]
1958年、神奈川県生まれ。アンソロジスト、文芸評論家。「幻想文学」「幽」編集長を歴任。ちくま文庫「文豪怪談傑作選」シリーズはじめ編纂・監修書多数。著書に『遠野物語と怪談の時代』(日本推理作家協会賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
72
明治末から昭和初期、文豪たちが怪談会に没頭していた。泉鏡花を筆頭に、柳田國男や芥川龍之介らが、怪談を語り合う。まるで自分が見たかのような怪談話。この当時、怪異はずっと身近にあったのだろう。ちくま文庫には文豪怪談傑作選のシリーズもあるようだ。そっちも読んでみたいなぁ。2020/08/01
sin
72
病床に在る鏡花の独白を触りに語られる各章に纏められた往年の百物語会に、曾て参加した熱く瑞々しい読者会の有り様を重ね合わせて読んだ。それにしても百年も前の彼等の怪談会に寄せる想いの新鮮味に、死して尚残る真実味は如何なる力の成せる技だろうと思わざるを得ない。とは云っても当時、神経で片付けられた幽霊の真偽は別である。それは在る意味共通の趣味で集うオフ会に似て場の共感で成り立っているように感じられる。2019/08/29
HANA
64
明治末から昭和初期、大正を中心に花開いた怪談会。本書はその熱気を鏡花を中心にまとめた一冊。最近は編者のものも含めてこの時代の怪談会の書籍が復刊されているんだけど、本書はある程度通史としての一貫性を保ちながらも、怪談会で語られた話もアンソロジー的に収録する事で読み物としての面白さと同時に当時の空気を表しているのが見事。幽冥界を中心にした鏡花や柳田国男、都会の怪異を語る芥川龍之介、そして数多の文人墨客たちの話を読みこういう集まりに思いを馳せていると、怪談というものが風雅の極みであるというのが納得できるなあ。2019/12/22
みやび
30
明治後期から昭和初頭にかけてブームが巻き起こったと言う「百物語怪談会」。そこに集まるのは一流の文化人達だった…。某新聞で連載された紙面において「怪談の親玉」と称された泉鏡花を筆頭に、柳田國男や芥川龍之介、菊池寛・徳田秋声・鏑木清方などなど、錚々たるメンバーが参加しているのが面白い。それもただ集まるだけではなく、出される食事から演出まで凝りに凝っている念の入れよう。収録されている怪談実話にゾクゾクしながらも、文豪と呼ばれる作家の交友関係や人となりを垣間見る事が出来てとても楽しい怪談語りだった。2019/09/22
❁Lei❁
20
夏といえば、怪談。そんな気分にぴったりのこの本には、泉鏡花をはじめとした文豪たちの怖い話がたくさん収録されています。明治から大正にかけて怪談ブームが起こっており、百物語などの怪談会で怖い話好きの人々が交流していたそうです。面白かったのは、枕元に現れた疫病神を睨んで退散させる話。柳田國男によると、疫病神にもいろいろ種類があって、中でも婆さんがいちばん厄介なのだそう。もし私も婆さんの疫病神に遭遇したら、「負けないぞ〜」という気持ちで挑もうと思います(あいにく、霊感はまったくありませんが)。2025/06/26
-

- 電子書籍
- CORRECT IMPACT【タテヨミ…
-
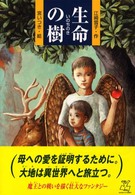
- 和書
- 生命の樹 ポプラの森