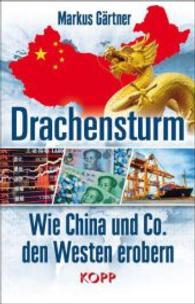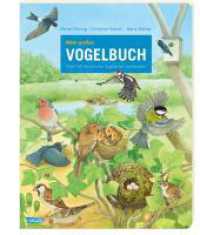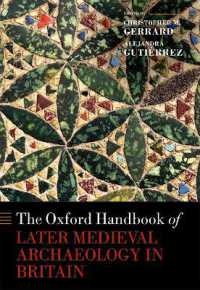出版社内容情報
非正規雇用や貧困で生きにくい社会。それとは別の社会を夢見る条件を作る。それが活動家の仕事だ。貧困問題に取り組んできた著者の活動史と現在。
内容説明
他なる社会の可能性を夢見てそれに形を与え、場を作り、共同性を練り上げ、夢見る条件を作る。これが活動家の仕事だ。2008年暮れから年明けの「年越し派遣村」や、2009年10月から2012年3月までの内閣府参与など、一貫して貧困問題に取り組んできた著者が、「活動家」についてわかりやすく伝える。
目次
第1章 NOと言える労働者に―派遣切りに抗して
第2章 生活保護の野宿者の現実
第3章 貧困は罪なのか?
第4章 自己責任論が社会を滅ぼす
第5章 ぼくは活動家
最終章 政権交代で問われること
著者等紹介
湯浅誠[ユアサマコト]
1969年東京生まれ。社会活動家。「反貧困ネットワーク」や、「NPO法人自立生活サポートセンター・もやい」等に関わる。95年から野宿者の支援活動を始め、貧困問題に関する活動と発言を続ける。2009~2012年内閣府参与。著書に『反貧困』(岩波新書、大佛次郎論壇賞受賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
40
自己責任論と貧困観についての文章に頬を張られる思いがした。自分の未熟な価値観を恥じた。この問題の本質に迫るためには、姿勢を根本的に変えねばならない。気付けたことで、とてもためになった。2015/07/17
ちさと
32
「結局私たちはナメられてきたのだ。主権は民にある。その原点を思い起こすべきだ。」貧困や過労の一部は自己責任にある。だけど経営者の、社会の、国家の自己責任はもっと大きいはずだという著者の主張は正しい。国家の存在意義は第1に国民の生命の安全だもの。この著作の主張や理論であれば、突き詰めれば「国民がバカ」という結論になるので、悲しい気持ちにはなる。正しいだけに辛辣。「活動家」故にか説明に客観的な要素が抜けていて、理想と現実性のバランスが悪い印象でした。惜しいなぁと思った1冊。2019/04/02
紫羊
21
私自身は、「自己責任論」を唱える大人たちに囲まれて育ったせいもあって、「人間努力すれば道は開ける」と信じていた時期もあった。でも、「うまく説明できないけれど何かが違う」という感じを持つようになり、やがて「反貧困」という本と、作者である湯浅誠さんに出会った。自分ではうまく説明できなかった部分を、湯浅さんは実にわかりやすく表現してくれた。それをさらに補強する一冊だった。このブレのなさに、あらためて活動家湯浅誠の凄味を感じた。2013/11/19
uD
17
目に見える範囲だと「日本は豊か」だと思ってしまうが、事実として貧困層は存在する。個人の責任を超えて当人を苦しめている現状をありありと伝えている本。 「貧困スパイラル=貧困問題と労働市場の崩壊は循環している」この論理に非常に納得、”NOと言えない労働者”が生まれる仕組みもここにあるのだと思った。 「貧困は自己責任ではない」という視点を持つことで、自分も得をする。なんて書くと損得勘定な感じがするが、結果的に社会全体が得をするのならそれでいいのではないかとも感じる。まずは知ることから始まるのだと実感した一冊。2019/03/29
たんたん麺
15
お金がなければアウト、非正規だったら負け組、恋人ができなければ人間失格、マイホームにマイカーがなければ甲斐性なし、病気をすれば自己管理が不十分、老後の貯蓄がなければ人生のツケ。国が企業を守り、企業が正社員を守り、男性正社員が妻子を守る。そのルート以外の守られ方は、自堕落・怠惰・甘え・努力不足・負け犬…。いい加減にしてほしい。この「いい加減にしてほしい」に形を与えること、形を与えるための”場”を作ること、そして他なる社会を夢見る条件をつくること。それが活動家の仕事だ。2014/05/11