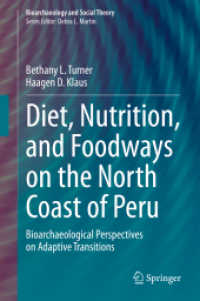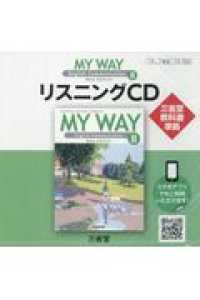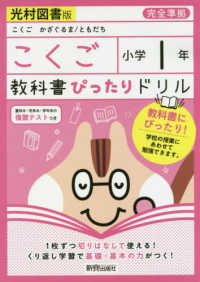出版社内容情報
『モナ・リザ』からゴッホ、ピカソ、ウォーホルまで、名画を前に誰もが感じる疑問を簡単すぎるほど明快に解き明かす。名画鑑賞が楽しくなる一冊。
内容説明
名画を前にして多くの人が感じる「どうしてこれが名画なの?」という疑問や戸惑い。そんな素直な感覚を出発点に『モナ・リザ』からモネ、マネ、ゴッホ、ピカソ、ウォーホルまで「見方の要点」を簡潔に解説、名画の魅力を明快に解き明かす。名画鑑賞が楽しくなる一冊。
目次
『モナ・リザ』の「!?」マーク―名画の中の名画に感動できない理由
現代アートの「??」マーク―これでもアートか??という気にさせる理由
モネのムラ塗り―好感度ナンバーワン印象派を代表する巨匠
マネのベタ塗り―スキャンダルの王者近代絵画のパイオニア
ドラクロアの色彩―印象派の色彩のルーツとなったロマン派の巨匠
レンブラントの陰影―ダ・ヴィンチと印象派をつなぐタッチと陰影
スーラの点描―現代メディアに先駆する色彩理論の実験者
ゴッホの渦巻―近代社会の病気を肩代わりした悲劇の画家
クリムトの平面―世紀末の美学を奏でる装飾の絵師
セザンヌの立体―美大入試の定番になった前衛手法
ピカソの自由―芸術の自由を象徴する二十世紀最大の画家
モンドリアンの厳密―モダン感覚が結晶する抽象絵画の最高峰
著者等紹介
西岡文彦[ニシオカフミヒコ]
1952(昭和27)年生まれ。多摩美術大学教授。版画家。柳宗悦門下の版画家森義利に入門、伝統技法「合羽刷」を徒弟制にて修得。雑誌『遊』の表紙担当を機に、出版の分野でも活躍。日本版画協会(’77)、国展(’78)新人賞、リュブリアナ国際版画ビエンナーレ50周年記念展(’05)招待出品(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





Ritzのざっくり本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
かな
Ai
bluemint
UK