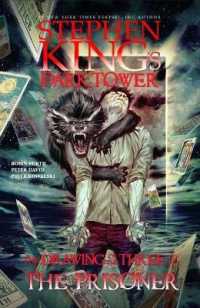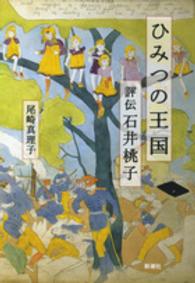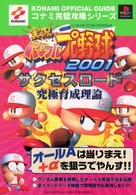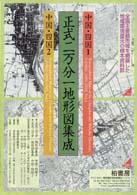出版社内容情報
「能」は、旅する「ワキ」と、幽霊や精霊である「シテ」の出会いから始まる。そして、リセットが鍵となる日本文化を解き明かす。
内容説明
能の物語は、生きている「ワキ」と、幽霊や精霊である「シテ」の出会いから始まる。旅を続けるワキが迷い込んだ異界でシテから物語が語られる。本書では、漂泊することで異界と出会いリセットする能世界、そして日本文化を、能作品の数々を具体的に紹介しながら解き明かす。巻末に、本書に登場する46の能作品のあらすじを収録。
目次
序章(台北での体験から;ワキがある「ところ」に行きかかり、シテと出会う ほか)
第1章 異界と出会うことがなぜ重要か(定家(一)不思議な墓
定家(二)心の秋 ほか)
第2章 ワキが出会う彼岸と此岸(無力なワキ;「旅」がワキのキーワード ほか)
第3章 己れを「無用のもの」と思いなしたもの(「空洞」な旅人;敦盛(一) ほか)
第4章 ワキ的世界を生きる人々(ワキ的世界に入れる人、入れない人;芭蕉は能の旅をしたかった ほか)
著者等紹介
安田登[ヤスダノボル]
1956年生まれ。能楽師、公認ロルファー(米国のボディワーク、ロルフィングの専門家)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ミカママ
484
もっと早くにこのご本に出逢いたかった。おワキが推しさまなくせに、ワキのことなんもわかってなかったじゃないか?!世間的にも「地味で」「脇役で」「いつもお坊さん」くらいの認識ではあるまいか。ワキの演者である著者ご本人も自嘲的に「シテ(主役級)の話を引き出すが、話を引き出し終わると、ワキの方で木偶のごとくひたすら座っているだけ」と(笑)でも実はワキは・・・というお話。過去の文人、漱石や三島、現代では春樹さまの文学も能だ、と語る。ね、能楽に興味のなかったあなたも読んでみたくなるでしょ(笑)そして旅に出たくなる。2024/10/03
獺祭魚の食客@鯨鯢
74
シテが生前の残した未練を観衆に訴えかける擬似怨霊とすれば、ワキはそのような悲運の人物への情感が強いスピリチュアルな存在だと思います。 西行や芭蕉が各地を紀行し、先達が残した記憶をたよりに往時を偲び歌を詠んだように、舞台上で主役であるシテの登場を促す役割を持っていると思います。 観衆は亡き人物への同情を通し自分に準えながら、個人個人の暗い過去へのカタルシスに達するのでしょう。2020/02/29
syaori
72
能は、ワキから見ると異界と出会う物語だと作者は言う。異界とは、神話的時間、穢れを払うハレの体験、「新たな生」の可能性を秘めるもの。でも、なぜワキだけが幽霊(シテ)と出会いそんな体験ができるのか。本書ではその鍵を能の詞章を参照しながら見ていきます。人生を思い切る、ワキ的立場に立つことは俗人には難しいのですが、ワキやシテの体験した人生の深淵は、死別など私たちの傍にもあるもので、その深淵を「共苦」することでその時間だけでも異界と出会うことができるという、芸術(異界)に触れる意義を教えてくれる素敵な本でした。2025/04/22
tonpie
46
初夏の頃、著者の「能」(新潮新書)を読み、9月に初めて佐渡島で薪能「鵺」を観ました。旅先で初めて能に接したことは、自分の後の人生に関わってくるような経験だったと思います。そんな興奮状態の中でこの本を読みました。これは、能の主役である「シテ」に対して「ワキ」を務める著者の視点から、「能とは何か」を、構造的に解き明かしてゆく話で、具体的な曲として「定家」「卒塔婆小町」「敦盛」を主に引き合いに出しています。また、能以外の文芸である芭蕉と漱石、そして三島「豊饒の海」も、「能の構造」を持っていると示唆しています。↓2024/09/13
Bo-he-mian
22
最近の思考が「能」に染まっているのは、この本のせい(にしてはいけないのだが・笑)。以前から気になりつつ、どこかとっつき難さを感じていた「能」が、実は自分自身が若い頃からずっと繰り返してきたそのものズバリなのだと気づかせてくれたのが本書。ここで云う能とは、超現実的存在が登場する「夢幻能」の事だが、その物語構造と精神性を判りやすく紹介。あ、能って要するに幻想文学なんだな、という当たり前の事に今更ながら気づいた。能楽師である著者の安田登氏は漢文の専門家でもあり超知識人だが、非常に読みやすい文章が素晴らしい。2021/06/21