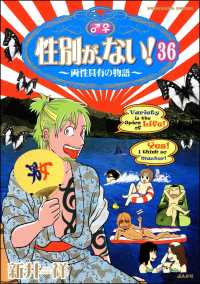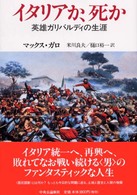出版社内容情報
内容は後日登録
内容説明
初等教育から大学まで、混迷する教育。意欲を失った子供や若者たち。学校は何のためにあるのだろうか?歴史を振り返ると、学校教育という制度は新しく、知識は「独学」によって各個人が自発的に獲得するものだった。しかも現在、IT技術の急速な進歩は時間と空間を圧縮し、「独学」の可能性はますます広がりつつある。「やる気」という視点から教育の原点に迫る。
目次
1(独学のすすめ;学ぶこころ;意欲の問題;読書について;生き方の学習;情報時代の自己教育)
2(教養とはなにか;お稽古ごと;「しごと」の意味;「問題」とはなにか;創造性というもの)
3(わがままな期待;試験の社会史;「専門」とはなにか;外国語の教育;学問の流動性;学校の意味―あとがきにかえて;あたらしい読者のために―ちくま文庫版へのあとがき)
著者等紹介
加藤秀俊[カトウヒデトシ]
1930年生まれ。東京生まれ。社会学博士。一橋大学を卒業後、京都大学、スタンフォード大学、ハワイ大学などで教える(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。