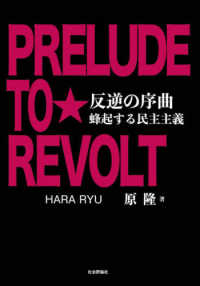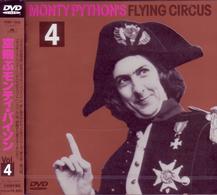内容説明
フラナリー・オコナーは難病に苦しみながらも39歳で亡くなるまで精力的に書き続けた。その残酷なまでの筆力と冷徹な観察眼は、人間の奥底にある醜さと希望を描き出す。キリスト教精神を下敷きに簡潔な文体で書かれたその作品は、鮮烈なイメージとユーモアのまじった独特の世界を作る。個人全訳による全短篇。上巻は短篇集『善人はなかなかいない』と初期作品を収録。
著者等紹介
オコナー,フラナリー[オコナー,フラナリー][O’Connor,Flannery]
1925‐1964。アメリカの作家。アメリカ南部ジョージア州で育つ。O・ヘンリー賞を4回受賞し、短篇の名手として知られる
横山貞子[ヨコヤマサダコ]
1931年生まれ。京都精華大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- 三国志 新武伝 DVD-BOX