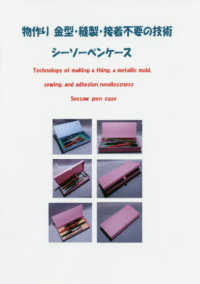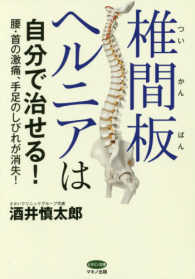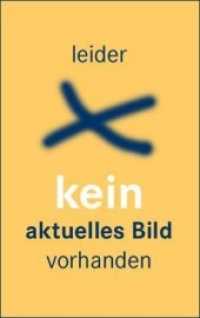内容説明
急速な高齢化に伴って、死はごくありふれたものになった。しかしどれほど科学が進んだとしても、死の向こう側は全く未知のままであり、その現実に触れることはできない。私たちはその必然にどう向き合えばよいのだろうか。松尾芭蕉や渡辺崋山、国木田独歩や夏目漱石、そして正岡子規や岡倉天心の遺書や辞世の句、死について書き残した手紙をもとに日本人の死生観を考える。
目次
序 死ぬのはいつも他人
1 序章ふたたび
2 国木田独歩の涙
3 夏目漱石の白雲吟
4 芭蕉の夢の枯野の吟
5 芭蕉遺書、臨終、“辞世”考
6 『おくのほそ道』、その位置と意味
7 辞世の歌と句さまざま
8 永訣かくのごとくに候
9 正岡子規の最期
10 岡倉天心と魂の恋人
著者等紹介
大岡信[オオオカマコト]
1931年静岡県三島市生まれ。東京大学文学部(国文科)卒業。読売新聞外報部記者、明治大学教授を経て、東京藝術大学名誉教授。その間、1979年から2007年まで「朝日新聞」に「折々のうた」を連載し、大きな話題を呼んだ。著書に『蕩児の家系―日本現代詩の歩み』(歴程賞)、『折々のうた』(菊池寛賞)、『紀貫之』(読売文学賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。