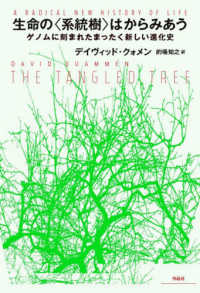内容説明
「熊を殺すと雨が降る」とはマタギに語り継がれる言い伝えである。山の神が聖なる地を熊の血で穢したことを怒り、雨を降らせて山を清くするという意味だ。だがマタギは裏の意味も知っている。熊は雨が降る前に食いだめをするため、この時に撃たれることが多いのだ。けれどもマタギは言い伝えどおりに記憶する。神の祟りを畏れたのだ―。山に暮らした人びとは、生態系の仕組みを科学の目では捉えなかった。そこに人間が自然と折り合いをつけて生きるための知恵を読み解き、暮らしの原点を克明に描いた快著。
目次
第1章 山の仕事(杣;日傭 ほか)
第2章 山の猟法(熊狩り;猪狩り ほか)
第3章 山の漁法(魚釣り;手掴み漁 ほか)
第4章 山の食事(魚;山獣 ほか)
終章 山の禁忌(口伝)
著者等紹介
遠藤ケイ[エンドウケイ]
1944年生まれ。自然のなかで手作り暮らしを実践しながら、日本全国、世界各地を訪ね歩き、人びとの生業や生活習俗を取材。子どもの遊び、野外生活、民俗学をテーマに、絵と文による執筆活動を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
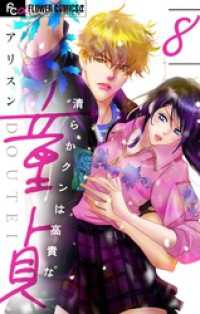
- 電子書籍
- 清らかクンは高貴な童貞【マイクロ】(8…
-

- 電子書籍
- 大預言者は前世から逃げる【分冊版】 1…
-

- 電子書籍
- 常識ハズレの最弱種~虐げられた最強勇者…
-

- 電子書籍
- 熱いレッスン【分冊】 10巻 ハーレク…