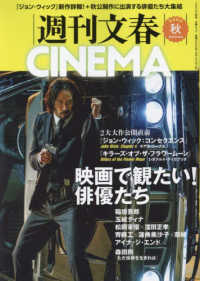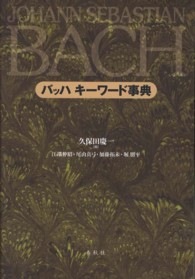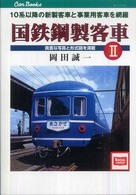内容説明
古今亭志ん朝が亡くなって失われたもの。それはその芸だけでなく、江戸の名残をうつす言葉。落語が決してフィクションではなく、日常の地続きであった時代の、東京に一貫して流れる「心」を映す言葉だった。江戸の文化と気風がいよいよ消える時期に際して、志ん朝のCDプロデューサーにして「江戸っ子四代目」の著者が、落語の名の「名文句」を題材に、そこに宿る江戸っ子気質を解読する。
目次
何を吐かしゃアがンでエ、べらぼうめエ―『大工調べ』
江戸っ子の生まれ損ない、金を貯め―『三方一両損』『文七元結』
それア、おれが悪かった―『百川』
まア、早い話が―『長短』
女のおれが見ていい女『三軒長屋』
半ちゃんは達引が強い―『酢豆腐』
ざまァ見やがれ、上げ潮の塵芥―『風呂敷』
あたしのほうがちがっているかも―『厩火事』
手が放されねエ―『小言幸兵衛』
妓がそばにいねエからってんで、ぐずぐず言うほど野暮な男じゃねエんだい―『五人廻し』
著者等紹介
京須偕充[キョウストモミツ]
昭和17年、東京生まれ。ソニー・ミュージック学芸プロデューサー時代に三遊亭圓生「圓生百席」の録音を手がけ、録音を渋っていた古今亭志ん朝が、唯一その高座の録音を許した。TBS系TV放映「落語研究会」解説も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。