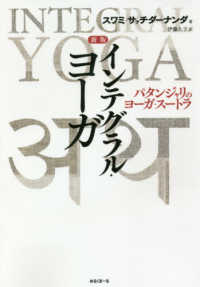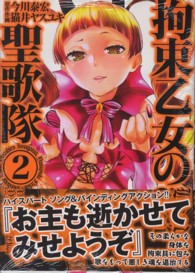内容説明
函館山の要塞、聯合艦隊の地下壕、幻の天皇御座所、天守閣の機銃痕、戦艦の主砲塔、岸辺にうち捨てられたトーチカ。終戦から60年余、消滅したかに見えた軍事関連遺跡は、各地に残っていた。けれども、それらの殆どは何の手だてもとられず、ひっそりと埋もれていた。近代の戦争と戦後のリアルな姿を記録した貴重な写文集!文庫書き下ろし。
目次
国境の町のトーチカ―根室(北海道)
山頂に眠る地下遺跡―函館山(北海道)
突貫工事の飛行場―茂原(千葉県)
鉄道聯隊の夢の跡―新京成線(千葉県)
最後の聚合艦隊司令部―日吉(神奈川県)
忘れ去られた記念碑―観音崎・横須賀(神奈川県)
幻の天皇御座所―松代(長野県)
六〇年、時を停めた空間―豊川(愛知県)
キャベツ畑の奇妙な塔―渥美(愛知県)
帝国海軍と赤煉瓦の町―舞鶴(京都府)
兵站基地と化した城塞―大阪城(大阪府)
明治期要塞の一級遺産―友ヶ島(和歌山県)
要塞島の数奇な運命―大久野島(広島県)
日本初の砲台公園―小島(愛媛県)
海軍の伝統を育んだ島―江田島・呉(広島県)
草生す東洋一の飛行場―大刀洗(福岡県)
三つ並んだ不思議な塔―針尾島(長崎県)
軍港を囲む明治の砲台―佐世保(長崎県)
海峡を睨む防人の島―対馬(長崎県)
掩体壕が物語る「戦後」―宇佐(大分県)
著者等紹介
竹内正浩[タケウチマサヒロ]
1963年愛知県三谷町生まれ。北海道大学を卒業後、日本交通公社に入社。出版部門で長年旅行誌などの編集に携わり、日本や世界各地を取材。2002年に退社し、フリーランス・ライター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
sasha
rbyawa
いちはじめ
映画屋
-
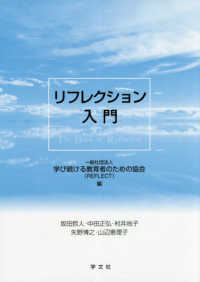
- 和書
- リフレクション入門