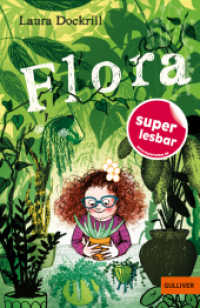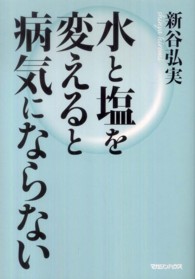内容説明
戦時下日本で反戦詩を書き続け、「抵抗詩人」と呼ばれた金子光晴のベスト・エッセイ集。本書では自伝と、アジア、ヨーロッパ紀行を収める。幼少時に若い養母に育てられ、早く性に目覚めた青年は、反抗と放蕩を繰り返した後、森三千代と結婚。三千代を巡る三角関係解消のために、夫妻は貧乏旅行に出発、数々の強烈な体験をする。だが、帰ってきた日本こそが「異国」だった。
目次
1 “鬼の児”世に憚る(洞窟に生み落されて;第一の「血のさわぎ」;大学遍歴)
2 愛と放浪の始まり(発端;恋愛と輪あそび;支那浪人の頃)
3 ヨーロッパへ(瘴癘蛮雨;処女の夢;ビールセル城;安土府)
4 ふたたびアジアの懐へ(マルセイユまで;疲労の靄;夜;虹;蝙蝠)
5 異国日本(腫物だらけな新宿;再びふりだしから出発)
著者等紹介
金子光晴[カネコミツハル]
詩人。1895年愛知県生まれ。1919年、処女詩集『赤土の家』発表後、渡欧。’23年『こがね蟲』刊行。翌年、森三千代と結婚し、’28年ヨーロッパ、アジアへ。’32年帰国。’37年『鮫』、’48年『落下傘』刊行。抵抗詩人と呼ばれる。’53年『人間の悲劇』で読売文学賞受賞。’75年死去
大庭萱朗[オオバカヤアキ]
1962年北海道生まれ。出版社勤務を経て、文芸評論家・フリー編集者として活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
81
『どくろ杯』『ねむれ巴里』他の著作から抜粋してまとめた本。金子が70歳あたりで書いたことを読み終えてから知った。解説の山崎ナオコーラが書いている。アジアやパリ、オランダに森三千代と旅行に行ったときの紀行文だ。金子光晴という詩人のことを知ったのは20歳の頃。とんがっていたつもりで読み、明治生まれのとんがり具合と繊細さにやられたことを思い出した。書かれているのは遠目に見たアジアではなくどろりとしたアジア、きらびやかなパリではなくすえた匂いのするパリだ。氏と同じくらいの年になってもういちど読んでみたいと思った。2019/02/05
hiratax
2
10年前に出てあっという間に絶版になったであろう文庫本で、解説は山崎ナオコーラが書いている。アジア放浪はコンテンツの一部、ヨーロッパでも東京でも金子光晴は所在なさげにうろついている。アジアの安宿で読めたのは良い。半年ぶりに訪れたヤワラーのはずれの旅社は、床がリニューアルされ、30バーツずつ値上げされていた。水シャワーは相変わらずであったが、暑気のため、このぬるさがちょうど良い。リニューアルをしたということは、当分この宿は当分は廃業する意思がないと見られ、いつまでここに来られるだろうかと思いをめぐらせる。2016/05/26
encore
1
すごくはっきりした人だしはっきりした文章を書くのにどこから書いているかわからないのが魅力。2014/03/21