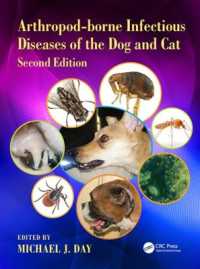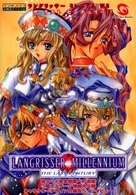内容説明
人生を左右する家づくりのキモとは何だろうか?長屋→アパート→マンション→建て売り→ロンドン・パリ生活を経た“お宅通”ビジネスマンが、「住宅の常識」に挑んで実現した家。著者の体験を読者がシミュレーションすることで、「家づくり」が自分の人生にとってどんな意味をもたらすのか、真剣に考えるキッカケになる。「住み心地」はもちろん「生き心地」もよくなる秘策がつまっている。
目次
第1章 あなたの“理想の家”には落とし穴がいっぱい
第2章 みんなが帰りたくなる「我が家」にしたい!
第3章 よい業者の“探し方”&“つきあい方”
第4章 「買う」ではなく「建てる」人だけが味わえること
第5章 家づくりは「生きざま」をも問うてくる
第6章 風合いのある家は「仕上げ」にかかっている
著者等紹介
藤原和博[フジハラカズヒロ]
1955年生まれ。杉並区立和田中学校校長。78年東京大学経済学部卒業後、リクルート入社。東京営業統括部長、新規事業担当部長などを歴任。96年より年俸契約の「フェロー」となる。2003年東京都で民間人初の公立中学校長となり注目を集める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ねお
20
家づくりとは、自分の人生に対して1000項目以上の質問状を受けること。筆者の業者選びの基準、見積もりの読み方、「ネオ・ジャパネスク」というコンセプト、解体リサイクルの行方やご近所付き合い、家づくりへの家族の参画等、参考になる点が多く、巻頭の自宅写真を何度も見返す。人が住む空間を作るということは、住む人の人生や価値観を表し、どのように生きたいかという考えを擦り合わせるということであるという意味がよくわかる。さらに、隈氏が住宅ローンに縛られた生き方や米の持ち家政策について解説する。どう生きたいか。難問である。2021/08/17
め
3
家を作るということはウン万もある組み合わせをしながらの創作活動で手を抜いたら抜いたぶんだけ妥協が生まれる。そして家というのは建てるのがゴールでは無く、出産でありスタート地点であると。中に住んで、メンテナンスや愛着が家を育てることになるという家の難しくもどかしさを感じるところ。実際の値段や葛藤、こだわりが書いてあって家を建てる際に再読しよう。2017/03/01
Ayumi Shimojoh
2
ブックオフ108円、2005年文庫化。作者の体験から奮闘録とノウハウを書き残した本。隈さんの解説より★家を買うな!=モノを買えばそこに付着したイメージも手に入れられる錯覚の全てを批判する。書斎を手に入れれば豊かな知的、文化的生活が手に入るという錯覚。アメリカが築いた20世紀の文明とは、そのような刷り込みを利用して商品を売るためのシステムだった。★3。私は家は有るものに住むタイプで、住環境の改善には熱意有りだが、この本で千本ノックに例える、家づくりは選択の嵐、に応えるエネルギーはない。2019/05/19
さきん
2
完璧に計算づくで建てても予想通りの生活が展開されるのではなく、意外な生活への刺激が生じていたりして、おもしろいと思った。ちょっとリッチじゃないとここまではできないと思う。2015/07/11
あんちゃん
0
新国立競技場で話題の隈研吾さんが解説に書かれている通り、「家を建てること」は、あくせくした日常生活でいつかはしっかり考えなきゃと思っている自分や家族の生活設計、人生観について、正面から向かい合う機会なんですよね。正直、藤原さんの様なエネルギーは私にはありませんが、これから家を持とうとする私は心構えだけでも参考にさせて頂きます。 2016/01/23