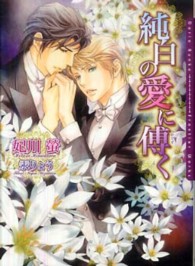出版社内容情報
モノやメディアが現代人に押しつけてくる記号の嵐。それに飲み込まれず日常を生き抜くには? 東京大学の講義をもとにした記号論の教科書決定版!
内容説明
社会やモノやメディアが現代人に発信してくる記号の嵐。それに飲み込まれず日常を生き抜くためには、どのような力が必要なのか。本書は、現代思想の基礎となるソシュールやパースの記号論から始まり、テレビCMや雑誌広告・アートと建築・身体と権力・ニュース報道・スポーツイヴェント・サイバースペースにおけるコミュニケーションの各論へと、11のレッスン形式で構成される。それらを通して、読者はセミオ・リテラシー、つまり「意味批判力」を獲得することができるはずだ。東京大学での講義をもとに書かれた、新しい記号論の教科書。
目次
モノについてのレッスン
記号と意味についてのレッスン
メディアとコミュニケーションについてのレッスン
“ここ”についてのレッスン
都市についてのレッスン
欲望についてのレッスン
身体についてのレッスン
象徴政治についてのレッスン
“いま”についてのレッスン
ヴァーチャルについてのレッスン
著者等紹介
石田英敬[イシダヒデタカ]
1953年、千葉県に生まれる。東京大学大学院人文科学研究科博士課程退学、パリ第10大学大学院博士課程修了。現在、東京大学名誉教授。専攻、記号学・メディア論、言語態分析。メディア・テクノロジーの発達と人間文明との関係を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
10
記号論には独立した二つの起源がある。ソシュールの記号学Sémiologieと米パースの記号論Semiotics、それが合流し記号論に。6章の都市空間を重点的に読む。都市を言語活動のように見る(ユゴー「コレがアレを殺す」活字本と大伽藍)。バルト「記号学と都市空間」で「都市は一個の言説」。我々は都市を生きることで(移動することで)意味を生み出している。『都市のイメージ』でリンチは、都市の構成要素五つを示す:通路、境、結び目、区域、目印。文法構造を解析するように都市の構造を把握していく。場の使用がそこに意味を与2020/12/29
きくらげ
6
後半は今読むと平成の振り返りみたいになってて懐かしさの感情しか湧いてこなくなる。NHKニュース7の映像や、各社のCMや広告のいちいちが時間の経過を伝えてくる。ネット黎明期のアバターもそうだし、サイバー空間が今ほど全面化する以前の時点での危機感の言説も同じく。平成っぽいといえば、記号に取りまかれた環境を一通り分析してみたあとにその向こうの光景を述べる段階になると、あれだけ他者の次元を強調しておきながらなぜか個の自律性や固有性、自分らしさといったワードに素朴に回帰してくるあたりも含めてそう、と言いたくなる。2025/09/22
amanon
6
六百頁を超える大部でありながら、平易な語り口に惹かれて、ほぼ一気読み。これだけの多岐に渉る内容を、殆どだれずに読ませるというのは、相当の力技と言えるのでは?ただ、理解の程はやや心許ないというのも事実。しかし、著者が後書きで示唆しているように、本書は今の我々を取り巻く世界について考えるためのメソッドというべきもので、一回読んで終わりというものではなく、事あるごとに立ち返るべき指南書だとも言えるのかもしれない。個人的にとりわけ刺さったのは、政治について語った9章だろう。これは教育に関わる人全てが読むべき。2024/01/06
taq
3
何十年ぶりに大学の集中講義を受けたような心地よい疲労をもたらす、内容がぎっしり詰まった良書だった。90年代の大学、院、市民講座などの内容をベースに書かれているので、取り扱われている例が古い(懐かしい)が、記号論の基礎的な考え方が分かるようになっているのでそこは問題ない。ソシュールやパースから始まって、社会を、幾つかの側面から記号論的に分析する具体的な手腕が勉強になった。折に触れて繰り返し読みたい。2023/10/11
でろり~ん
2
初著者。読み終えるのにすごく時間がかかりました。内容はサイコーに好い講義だったと思います。日常生活の中で、自分自身で考えるためのポジションを、まずは見極めないといけませんね。ミーニング・オブ・ライフって、やっぱり難しいってことですねえ。再読しないと、ホントには理解できない感じですが、再読するかな? どうかな? って感想でした。2021/03/03