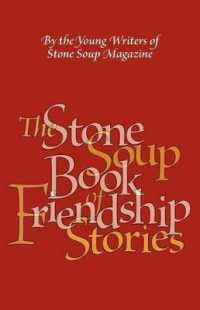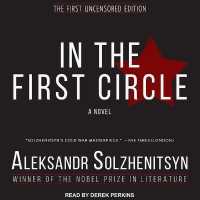内容説明
どんぶり物を生み出したのは、江戸時代に生きたある男の“食い意地”だった。出前の蒲焼が冷めないようにと、蒲焼をご飯の中に入れ込んで楽しんでいたところ、それがまわりにも広まり、日本初のどんぶり物、うな丼が誕生する。それまで白いご飯の上におかずをのせるという発想を持っていなかった江戸っ子たちは、すっかりうな丼の虜となった。だがうな丼以降、新たなどんぶり物が誕生するには時間がかかった。天ぷら蕎麦や親子とじ蕎麦は江戸時代には生まれているのに、天丼や親子丼の登場は明治になってから。その背景には何があったのか?膨大な史料から、どんぶり物誕生の歴史をひもとく。
目次
序章 どんぶり物が生まれるまで
第1章 鰻丼の誕生
第2章 天丼の誕生
第3章 親子丼の誕生
第4章 牛丼の誕生
第5章 かつ丼の誕生
著者等紹介
飯野亮一[イイノリョウイチ]
早稲田大学第二文学部英文学科卒業。明治大学文学部史学地理学科卒業。食文化史研究家。服部栄養専門学校理事・講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koji Eguchi
63
めったに読まない解説本?!★★☆。丼はどれも好きで、生まれた順番やその経緯は興味深かった。前の方は古文も一応読んでみて解説で理解していたが、後ろの方では古文を読むのに疲れてきてすっ飛ばした。しかし古い文書にいろいろ記載が残っているもんだね。当時の看板を沢山記録しているのなんて、よくぞ残してくれたという感じ。日記に書いたなんてことないその時の食べたものが重要な記録になっている。明治時代の文明開化と切っても切れない洋食の拡がりは、当時の市民の活性を感じさせる。昔の丼がどんな味だったのか食べてみたい。2020/04/02
ホークス
50
2019年刊。5種の丼物の誕生と普及の流れを丁寧に語る。当時の品書きや屋台の絵も楽しい。鰻の蒲焼きは元禄年間には酒肴として売られた。飯で食べさせる店は、タレに味醂を使って大流行。明治に鰻の養殖が始まり大衆化する。親子丼は意外に難産だった。長らく鶏肉はタブーとされ、卵は食べて良いけど高価。親子丼最古の品書き(神戸の江戸幸)は明治のもの。天丼は天茶より後に登場。寛政年間に様々な茶漬店が流行り、立食い店の天ぷらを取り入れた。牛丼は安さもあり、関東大震災直後に凄まじく売れて被災者を救った。日本人は昔から牛丼好き。2022/09/13
どぶねずみ
41
明治時代を中心に丼料理ができるまでの歴史から、食肉文化が誕生するまで幅広い雑学。この本の参考文献もものすごく多い。元々観賞用だった庭鳥が食用の鶏になったり、ご飯のうえにおかずをのせるとか、玉子でとじるという食文化もなかった江戸時代。鰻が覚めないようにご飯と一緒にお重に入れて鰻重は誕生したことが、全ての丼料理の始まりらしい。丼食べた~い。2019/12/11
みつ
38
「日本五大どんぶり」の誕生の歴史を辿る本。扱う順は、歴史に沿って、うな丼、天丼、親子丼、牛丼、かつ丼となる。江戸時代の江戸で多く白米が食べられ(それゆえ脚気を「江戸患い」と呼んでいたともどこかで読んだ)、丼が出来る素地もありそう。ただし、うな丼以外がすべて明治以降に出来上がったとは少々驚き。屋台が多くあった天ぷらさえも、天そば、天茶漬けが先行したとのこと。うな丼に割り箸が不可欠な理由、親子丼では卵の方が鶏肉よりも高価など、食欲をそそる記述が満載。持病のため炭水化物である米食は控え気味なのがつくづく残念。2025/03/05
Shin
25
題字のフォントとあいまって今年読んだ本の「タイトル・オブ・ザ・イヤー」に認定したくなる。主に江戸以降の文献を紐解きながら、日本5大丼の誕生の経緯を探る楽しくも真面目な食文化史。丼が主題ではあるが、江戸や明治の人々が少しでも美味しいものを食べよう、食べさせようとした記録の中に、とても生き生きとした日本の近代史が浮かび上がってきて上質な歴史ドキュメンタリーにもなっている。親子丼の章の「鶏の親子の間を長い間隔てていた壁が、明治維新という新しい時代の波によって打ち砕かれたのだ。」というクダリが大好き。2019/10/06
-

- 電子書籍
- 危険な相続人 (下) 角川文庫