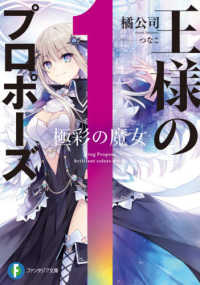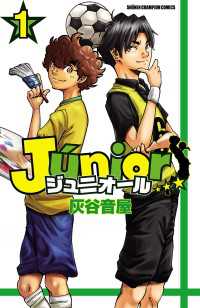出版社内容情報
素読とは、古典を繰り返し音読すること。内容の理解は考えない。言葉の響きやリズムによって感性を耕し、学びの基礎となる行為を平明に解説する。
内容説明
「素読(そどく)」とは、内容の理解は後まわしにして、古典を繰り返し音読すること。江戸時代以来、学習の初歩として行われてきたが、これには確かな意味があった。言葉の響きやリズムに浸ることによって感性が磨かれ、学びを深めるための土台をつくるのだ。また、素読は外国語の習得にも効果を発揮する。本書では、著者が子どもたちと実践してきた経験をもとに、素読の具体的な方法や外国における音読の例などをていねいに解説していく。声に出して読むことの意義をいちはやく再評価した書。
目次
第1章 素読を支えるもの
第2章 外国語早期教育と漢文素読
第3章 素読の歴史とさまざまな例
第4章 ヨーロッパでの経験
第5章 ユダヤ教の聖書朗詠
第6章 素読を始めるにあたって
著者等紹介
安達忠夫[アダチタダオ]
1944年、福島県平市(現いわき市)生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修了。埼玉大学名誉教授。専門は、ドイツ・北欧文学および児童文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
anarchy_in_oita
7
最近資格の勉強に多くの時間を割いており、その上いくつかの本を同時並行でダラダラ寝る前に読んでいるだけなので、一気に本を読み通したのは久しぶりな気がする。筆者の経験から始まり、福沢諭吉は〜ロックは〜デリダは〜といった具合に、世界各地の先賢が持っていた豊かな古典の素養を列挙されると、嫌でも素読はいいことだと納得せざるを得ない。僕は「読書百遍」のような読み方をかつてしたことがないが、味読に足るような書物にこれから出会ったときは意識してそのような読み方をしてみたい。離騒を暗唱してみるか2020/04/30
ゆたか
3
「聞き流すだけで○○語が身に付く」と喧伝している教材よりも、噛み応えのある文章を何度も何度も素読することで自分の血肉にしていくことの方が自分の力になる、と思いたい。2018/03/14
ご〜ちゃん
3
素読にまつわる著者の考えや体験が描かれていて、一気に読めた。素読をするというハードルの高さが大きく下がった。反復と持続が大切ということだが、まず自分でやってみようと思った。2017/11/12
ひろみんぐ
2
理解を重視する学習が中心の現代に於いて、寺子屋で行われていた素読(理解はひとまずおいて音読すること)の重要性を語っている。そうすることで、言語を学習する土壌ができるらしい。2019/03/24
良さん
2
素読、音読の効用について、歴史的、実証的に解説。外国語学習や聖書、ヨーロッパの古典など、全世界の文化の中に息づく素読についても触れている。 【心に残った言葉】わたしたちが、ことばの真実を回復するためには、まず、ことばに対して謙虚にならなければいけない。(215頁)2018/02/15