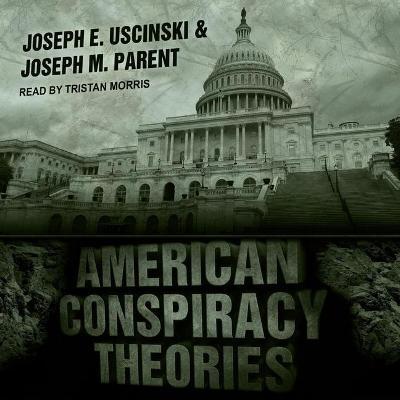出版社内容情報
二八蕎麦の二八とは?握りずしの元祖は?なぜうなぎに山椒を?膨大な一次史料を渉猟しそんな疑問を徹底解明。これを読まずして食文化は語れない!
内容説明
日本料理の基礎が出来上がった江戸時代。後期に入り経済事情が安定すると、ふだんの食事にも胃袋を満たす以上のものが求められるようになる。こうした中で生まれ、洗練されていったのがすし、天ぷら、蕎麦、うなぎだ。腕利きの料理人が現れると、食べ手にも粋人が現れる。この両者が出会い、食の世界に変革がもたらされていった。たとえば、日本橋南詰の天ぷら屋台の名店「吉兵衛」の客が、隣り合わせた屋台のかけ蕎麦に天ぷらを浮かべることを思いつく、といった具合に―。膨大な史料を読み解き、江戸四大名物食誕生の知られざる歴史に迫る、江戸食文化史の決定版!
目次
序章 食べ物商売の繁盛と四大名物食
第1章 そば屋の誕生と発展(そば屋の誕生;そばの名店の誕生 ほか)
第2章 蒲焼屋の誕生と発展(蒲焼のはじまり;蒲焼屋と江戸前鰻 ほか)
第3章 天麩羅屋の誕生と発展(屋台店で売りはじめた天麩羅;天麩羅屋台店の繁盛 ほか)
第4章 握りずし屋の誕生と発展(握りずしのルーツはなれずし;江戸の町にすし店あらわる ほか)
著者等紹介
飯野亮一[イイノリョウイチ]
早稲田大学第二文学部英文学専攻卒業。明治大学文学部史学地理学科卒業。食文化史研究家。服部栄養専門学校理事・講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
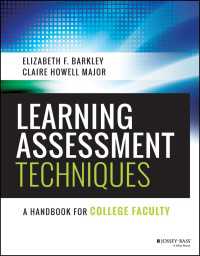
- 洋書電子書籍
- 大学のための学習評価手法ハンドブック<…
-
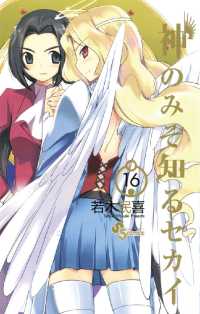
- 電子書籍
- 神のみぞ知るセカイ(16) 少年サンデ…