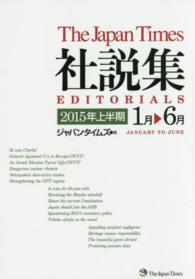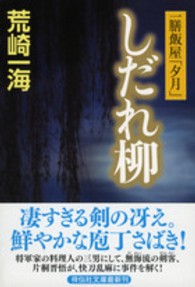出版社内容情報
日常の「自明と思われていること」にはどれだけ多くの謎が潜んでいるのか。哲学の世界に易しく誘い、その歴史と基本問題を大づかみにした名参考書。
内容説明
哲学とはどういう学問なのか?科学も答えてくれない人間をめぐる謎を、哲学はどのようにして解き明かすのか?日本を代表する哲学者がやさしく解説。第一部ではソクラテス以前に遡る西洋哲学の誕生から、現代までの歴史を大づかみ。第二部では、いまを生きるために避けて通れない問題―自然とのかかわり方、心と身体の関係、死との向き合い方など―をテーマごとに丁寧に考察する。数ある入門書のなかでももっとも基礎の基礎から説きおこし、自分の頭で問いを掘り下げる哲学的思考へと誘う名テキスト。
目次
第1部 哲学とは何か(哲学の誕生―神話的・呪術的思考と哲学;西洋哲学の展開;現代哲学の諸傾向とその問題点)
第2部 現代に生きる人間と哲学(人間における自然と文化;心と身体;哲学における死の問題;人間の社会性;人間の自覚としての哲学―むすび)
著者等紹介
木田元[キダゲン]
1928‐2014年。中央大学教授、名誉教授。戦後日本を代表する哲学者。ハイデガー、メルロ=ポンティを中心とした現代哲学を専門とする
須田朗[スダアキラ]
1947年生まれ。中央大学教授。カント、ハイデガーなどドイツ近現代哲学が専門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件