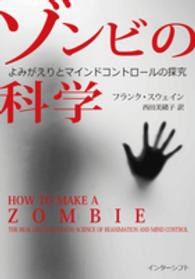出版社内容情報
日本は決して「一つ」ではなかった! 中世史に新次元を開いた著者が、日本の地理的・歴史的な多様性と豊かさを平明に語った講演録。
内容説明
日本の地理的・歴史的・社会的な多様性や豊かさをわかりやすく語った歴史の常識をくつがえす幻の名講義。
目次
第1章 日本史の転換点としての中世―東国と西国(内藤湖南の発言をめぐって;若狭の漁村に見る日本の中世像 ほか)
第2章 “無縁の原理”と現代―『日本中世の民衆像』と『無縁・公界・楽』を読んで(質疑応答 私にとっての戦時期と戦後一〇年;ワク組みのなかでの思考 ほか)
第3章 新たな視点から描く日本社会の歴史(日本人とインディオの共通点;「農民」と「非農業民」 ほか)
第4章 日本人・日本国をめぐって―中世国家成立期の諸問題(「日本民族」とは;「日本論」再検討の必要性 ほか)
第5章 時宗と「一遍聖絵」をめぐって(「一遍聖絵」の時代背景;都市的な場の出現と市庭 ほか)
著者等紹介
網野善彦[アミノヨシヒコ]
1928‐2004年。山梨県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。名古屋大学助教授、神奈川大学短期大学部教授、同大学特任教授を歴任。歴史家。専攻は日本中世史、日本海民史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
22
ずっと積読になっていた『無縁・公界・楽』に繋げようと読んでみました。講演記録なので読みやすいですけど、質問者は専門家なのでなかなか突っ込んだ質問をしています。中世の土地所有の隷属ではなくて、土地を自由に行き来する無縁社会の人々。昨日『瞽女』という映画を見たので、その解説としても面白かったです。瞽女は盲目に生まれたけど、自立した生活をするために瞽女になるのです。その瞽女社会は家と縁を切られた者が集って瞽女の社会を作り出す。2021/05/21
中年サラリーマン
17
「日本の歴史をよみなおす」の方がインパクトがあったがこちらは講演形式なので平易で読みやすいです。2014/04/20
金吾
16
日本の歴史に広く網をかけたように感じる一冊です。他の著書でも触れられている日本人とは何かとか租税に関する話は面白かったです。2021/05/29
moonanddai
9
以前から感じていることですが、ここで使われる自由という用語、相当昔からある言葉であるようなのですが、個人的には近代的なイメージを持ってしまいます。中世(あるいは古代から?)でいう自由とは、(網野氏によれば)下人とか所従とか言われる隷属した身分ではなく、「ある共同体の成員権を持った人」であること、をいう…。共同体の成員であるからこそ税(租庸調みたいな成文化されたものや「贄」といった慣習的なものまで)負担に耐えることは、共同体つまり「公」ひいては天皇までも支えているという意識を持つことなのだと…。フーム…。2023/10/24
トンボ玉
6
自分の歴史的興味は奈良・飛鳥時代から始まりました。日本書紀を読む中で様々な疑問が頭を擡げ、大和朝廷の出来上がる前にと手を拡げていきました。今回初めて中世史家網野さんの本を読みましたが、強く感じたのは「この人は何と闘っているのだろう?」という疑問でした。先住民問題を語り、部落問題と繋がる非人を語り天皇制を語る。彼は歴史の真実を追求してるのでなくて、歴史学会に流れている「常識」と闘っているのではないのかと。 また途中どうしても引っかかるのが今の皇太子を呼び捨てにすることで、政治的な意図を感じざるを得ません。 2014/05/20