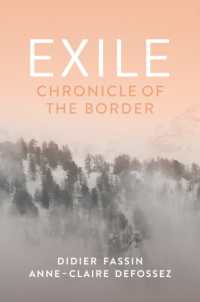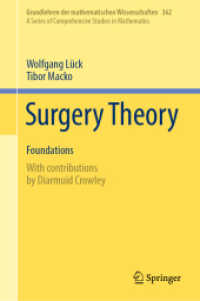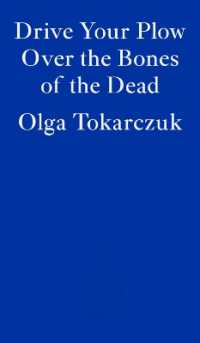出版社内容情報
産業が必要とする技能は、どこで、どのように獲得されたのか。学校、会社、軍隊など、近代日本を支えた人的資源を造ったシステムの中核を探る。
猪木 武徳[イノキ タケノリ]
内容説明
天然資源が豊かではない日本にとって、人材の重要性は強調してもし過ぎることはない。経済的豊かさを規定するのは「人」であり、「人」しかない。では近代日本の経済発展を人材形成の歴史として読みなおしたとき、どのような特徴が浮かびあがるのか。本書では、経済成長をもたらした人的資源(human resources)の形成と配分を、学校、会社、軍隊などの教育・訓練の姿を中心に検証する。「持たざる国」日本では、知識と技能はどのように修得され、産業活動の現場に動員されたのか―。江戸期から現代への変遷をたどり、歴史と理論の両面から日本のシステムの核心に迫る。
目次
第1章 江戸の深さ、明治の新しさ
第2章 工業化と労働力
第3章 軍隊と産業
第4章 戦後の学校
第5章 工場内の人材育成
第6章 高学歴化したホワイトカラー
第7章 官吏から公務員へ
第8章 移民と外国人
著者等紹介
猪木武徳[イノキタケノリ]
1945年滋賀県生まれ。京都大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ工科大学大学院修了(Ph.D.)。大阪大学経済学部長を経て、国際日本文化研究センター所長。2016年3月まで青山学院大学大学院特任教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-

- 和書
- フランス革命と科学者たち