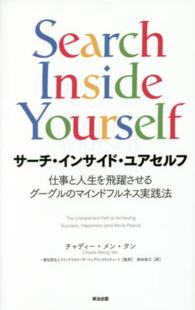出版社内容情報
近代国家において愛国心はどのように発展したのか。共同体への愛着が排外的暴力とならないために何が必要か。著者の問題意識が凝縮した一冊。
内容説明
日本人の忠義は本質的に孤忠(忠義の独占)であり、戦前・戦時中の愛国心は、天皇への愛情と奉仕から成り立っていた。本書はこの愛国心が、頬かむりしたまま戦後も利用されていることへの危惧から執筆された。まず国民国家の成立までを概観し、狭義の愛国心=エスノセントリズム(自民族中心思想)が個人の確立と民主主義によって合理化されていく過程が示される。フランス革命当時、愛国者とは国を愛する者という意味ではなく、自由主義的精神の持主を指す言葉だったのだ。そして寛容と愛情―結合しがたいこのふたつのものを結びつけていくところに、愛国心の積極的な意味を見出す。
目次
1 問題としての愛国心
2 愛国心とは何か
3 愛国心の歴史
4 愛国心と民主主義
5 愛国心の呪詛
6 新しい展望
『愛国心』前後
愛国心について
著者等紹介
清水幾太郎[シミズイクタロウ]
1907‐88年。東京生れ。東京帝国大学文学部社会学科卒業。社会学者。ジャーナリスト、文学博士。讀賣新聞社論説委員、二十世紀研究所所長などを経て、学習院大学教授(1949‐69)、清水研究室主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。