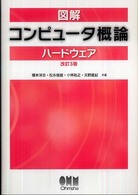出版社内容情報
文明開化以来、日本は西洋と対峙しつつ独自の哲学思想をいかに育んできたのか。明治から二十世紀末まで、百三十年にわたる日本人の思索の歩みを辿る。
内容説明
明治以来、日本人は何をどのように考えて来たのか?近代の始まりとともに、西洋の思想や文化を積極的に受け入れるようになると、それらの思想と対決しながら内面化し、独自の哲学を築き上げる思想家が数多く現れた。本書は国内外の状況が目まぐるしく変わっていく時代、19世紀後半から20世紀末にいたる歴史に足跡を残した哲学者・思想家たちの主要著作と思索のエッセンスを紹介。福沢諭吉、西周らに始まり、岡倉覚三(天心)、西田幾多郎、田邊元、和辻哲郎などを経て、務台理作、中村元、井筒俊彦、湯浅泰雄らに至る流れを総覧する。日本の哲学思想史を概観するのに格好の入門書。
目次
第1部 明治・大正・昭和前期(第一期・解放と啓蒙―文明開化の流れ;第二期・近代日本哲学の諸様相―観念論の潮流と講壇哲学)
第2部 第二次世界大戦敗戦以後(第一世代・対決と解放;第二世代・理性から感性へ)
著者等紹介
濱田恂子[ハマダジュンコ]
1932年生まれ。東京大学文学部独文学科・倫理学科卒業。同大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。関東学院大学名誉教授。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
9
新刊棚より拝借。福澤諭吉先生の思想では、女性の権利を保障していくことにポイントを感じた(029ページ)。今の女性手帳と比べて、少子化問題もあるにせよ、改めて考えさせられる。岡倉覚三、内村鑑三らの紹介、分析も。九鬼周造と美学。「いき」の大和民族文化の特性(145ページ)。いきは解釈的。いきは細い縦縞(146ページ)。河上肇は、内村鑑三から影響され、農業経済学を修めるも、無我庵の活動に傾倒(162ページ~)。湯浅泰雄とヘリゲル『弓と禅』(334ページ)。著者は哲学が哲学研究の隘路にあると批判(352ページ)。2013/06/13
isao_key
6
元タイトルは『近・現代日本哲学思想史』(2006)を文庫化したもので、内容的には元の方がぴったりなのに、なぜ変えてしまったのだろう。明治から現代までの日本人の哲学者と呼ばれる人を紹介している。なので文芸評論家を兼ねている丸山真男、鶴見俊輔、吉本隆明、小林秀雄などは取り上げられていない。だが中村真一郎は紹介されている一方、柄谷行人、蓮見重彦、竹田青嗣はないので、基準がよく分からない。ただ明治期の思想家を紹介する本はあっても現代を扱っている本はほとんどないので、価値はある。中村元先生の言葉は、今でも重い。2015/11/20
うえ
6
福沢諭吉から中江兆民、西田哲学から中村雄二郎、湯浅泰雄まで広範囲を扱う。一人一冊まるごと要約で大変便利。著者の苦労が偲ばれる。「大戦後には、機会均等の理念に従い、アメリカに倣った教育体制に改められた。全体としての教育水準は高まったが…高等教育段階では、残念ながら改革の成果は偏った…貴重な体験として受け止められた哲学教育はその場を失い…社会科が取って代わり、青春時代に哲学的関心に目覚めて…論理的に展開する訓練の場が失われたのである。学生紛争がたけなわであった60年代にはこの改革も影響を及ぼし始めていた」2015/08/22
左手爆弾
3
まず分量が豊富で、なんと明治初期から21世紀までの仕事を手広くカバーしている。「近代日本思想史」という表題の割りに、ほとんどが哲学者の哲学的業績なのはややずるい気もするのだが、取り上げ方は非常に丁寧で、有名な哲学者についてはあえてあまり取り上げられることがないが重要な著作を扱ったりするなど、工夫も随所に見られる。良書であることは間違いない。が、それだけに、最後で現状の日本哲学界へのやや紋切り型の批判になってしまったのは残念である。哲学がある種の危機に瀕しているのは間違いないが、それは常にそうであろうから。2015/06/02
ぽん教授(非実在系)
2
主に哲学についてを福沢から扱い、最後には鷲田清一まで出てくるなど扱う範囲が明治~現代である。限られたページ数で多くの人物を扱っているためそれぞれの説明はややコンパクトながら隙がなくポイントの多くを網羅しており情報密度は高め。参照用に役立つこと間違いないが、タイトル通りに入門用に使えるかと言われるとむしろ違う気がする。どちらかというと再入門用。2015/10/30