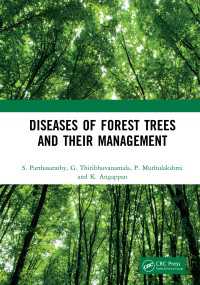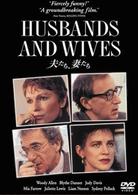内容説明
「人間」とは、自由で平等な近代社会を作るための発明品だった。そして、それは理性的で主体性をもつ個人のはずだった。ところが、巨大化し機械化する都市の孤独のなかで、この人間たちは気づかされる。「理性と主体性のある「私」なんて嘘だったんだ!」このときから「人間」は「非人間的」な存在へと急速に劇的に変貌していった。「自由な個人」から「全体主義的な群衆」へ、「理性的な主体」から「無意識に操られる客体」へ。何がどのようにして起こったのか。その思想的背景を、キィワードごとに、壮大なスケールで描きだす「非人間」化の歴史。
目次
文庫版序文に代えて―3・11のクロニクル
はじめに―「人間」という逆説
序章 アウシュヴィッツへの旅
第1章 全体―個から全体へ
第2章 無意味―アヴァンギャルドからファシズムへ
第3章 未開―岡本太郎「太陽の塔」の謎
第4章 無意識―理性から狂気へ
終章 幼年期の終わりを越えて
アフタートーク メディア―現実とイメージの逆転
著者等紹介
塚原史[ツカハラフミ]
1949年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、京都大学大学院仏文科修士課程修了、パリ第三大学博士課程中退。現在、早稲田大学法学部教授。前衛芸術から全体主義をへて消費社会へといたる20世紀文化の展開に鋭い視線をむけている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
左手爆弾
3
テーマは面白いだけに、きちんと歴史的に分析的な記述をしてほしかった。実際の中身は、ポエム調文体でのエセーと、芸術評論が多い。副題はバカロレアの課題からとられたもので、ここに焦点を合わせればもっと読みやすかったのだが、「機械」や「群衆」の話をきっかけに脱線しはじめ、岡本太郎論までいってしまう。しかも、芸術の話は著者の別の本と被る箇所も多く、しかもそちらの方がわかりやすかった。個人と群衆は対概念であるようで補完的であるというテーゼをもっと回収すべきだったように感じた。2017/12/09
dilettante_k
3
11年著。00年のちくま新書版に文庫版序文「3.11のクロニクル」等を付す。18世紀に誕生した理性的「人間」は、なぜ今日に至るまで数々の「非人間」的行為に傾斜してきたのか。20世紀の思想が発見してきた全体(主義)、無意味、未開、無意識といった非人間像を辿り、その実相を読み解く。西欧的人間ー非人間の対応を、近代と反近代、自己と他者などの関係性に読み替えながら、現代は差異のコーディングによるシミュレーションの時代(ボードリヤール)に突入したと指摘する。人間像をめぐる西欧の知的葛藤をダイナミックに描出した良書。2014/09/01
1.3manen
3
孤立感(ロンリネス)と孤独(ソリチュード)との違いは、ハンナ・アレントに求められるという(092ページ~)。前者は他者といる方がかえって強く感じられるという。無縁社会、孤独死の問題が徐々に深刻化している日本であるが、その淵源は20世紀からきているのか。冒頭で、3.11のクロニクルがあるが、不安の日常化が、見えない膜のように日本全体を覆っている(012ページ)との実感は共感できる。昨年は右往左往しているが、今の日本は田舎だからか余計に静かなものだ。文明の終着駅原発事故の後の健康への不安が徐々に、心を蝕んだ。2012/11/30
がんちゃん
2
太陽の搭に関する考察が面白い。2018/09/09
らむだ
1
Cf.2012/07/24