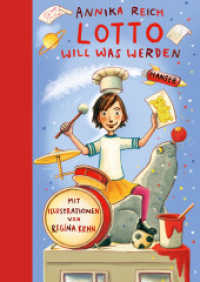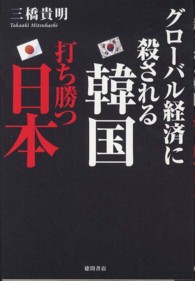内容説明
岩手県遠野―山深き地でありながら、古くから交易の要衝として栄え、懐に豊かな伝承と記憶をいだいて生きてきた里。この地に生まれた佐々木喜善が柳田国男に故郷の伝承を語って聞かせたことから名著『遠野物語』が誕生し、日本の民俗学が出発した。喜善はその後も長い時間をかけて遠野の伝承・昔話を掘り起こし、記録しつづけ、のちに「日本のグリム」と讃えられる存在となる。その仕事の集大成といえる本書には、いにしえの日本に息づいていた不思議な、愉快な、奇想天外な、あるいは怖い物語がぎっしりと詰まっている。日本人の心の故郷ともいうべき珠玉の物語集。
目次
聴耳草紙
観音の申子
田螺長者
蕪焼笹四郎
尾張中納言
一目千両
炭焼長者
山神の相談
黄金の臼
尽きぬ銭緡〔ほか〕
著者等紹介
佐々木喜善[ササキキゼン]
1886年、岩手県に生まれ、1933年没。医学校に入るが、2年で辞し、上京。哲学館(現、東洋大学)に入学し、のち早大文科に学ぶ。文学を志すが、柳田国男と出会い民俗学に転じ、生涯昔話の発掘に専心する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
10
温泉旅行のついでに立ち寄った遠野の里の伝承園のお土産物屋さんで衝動買い。佐々木喜善は柳田国男のインフォーマントとなった人で生涯、民話収集に取り組んだらしい。東北の農民の口調を共通語の中に生かそうとする文体は、彼の郷土の人々と風俗、自然への愛を伝えている。味読に相応しい一冊でした。2024/11/09
いとう・しんご
9
折々に読み進めて気がついたら再読。M.ウェーバーは「職業としての学問」の中で学問の世界で実績を上げられるかどうかは運次第、と言っていたけれど、佐々木喜善という人は、結局は運が無かったんだなぁと思うし、それで善いと思っていたような気もする。柳田や折口と比較するととりわけそんな気がする。・・・雨の日に読み終えるのに相応しい、シミジミした本でした。2025/04/01
アカツキ
9
岩手県遠野を中心に収集した昔話集。おじいちゃんおばあちゃんが孫に話しているのを隣で聞いているような読み心地。方言っていいなぁと感じる。ずっと読んでいたくなるほど面白かった。122番・端午と七夕の、悪人に騙されて夫が浮気していると思い込んだ妻が入水、帰宅した夫は妻のフレッシュな溺死体を食べ始める…?唐突なカニバリズムにびっくり。食べたいほど妻を愛していたのか、お腹が減ったけれど妻の死体以外食べられそうなものがなかったのか。女が人を食べて鬼になる話はいくつもあるけれど、男が人を食べて鬼になるのは覚えてないな。2023/11/08
ぽん
5
親から子や孫へ語り継がれて来たこの国の物語たちの豊かさに嬉しくなり、その物語の裏側や歴史を考えさせられ、一人のある人物の偉業とその現実に想いを馳せる。民族学的や学問として意味ある物語集なのでしょうが、この豊かさを物語として次の時代にも伝えていけたらいいなあ、と思います。2013/06/30
乃木ひかり
3
小さい頃絵本で読んだ物も多くあり、あらためて絵本の重要性を確認。もう誰も知らない話が各地にどれくらいあるのか考えると切なくなるが、少しでも残せたらと思う。2016/01/26